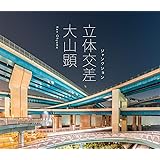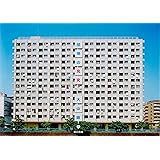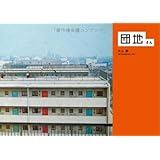まず、図書館で借りたのですが
ただぼんやり高架下を写したものでなく
大変に建物の様子、意図を伝える
良い写真ばかりなので
探して購入。
少し前の本なので諦めていたが
大変に美品を届けていただき
感謝です!

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

高架下建築 単行本(ソフトカバー) – 2009/3/3
大山 顕
(著)
団地や工場、ジャンクションの写真集でもおなじみの著者が贈る世界初、高架下建築写真集
いつも乗っているあの電車の下には、こんなに素敵な世界が広がっていた!鉄道好きな人たちも、上ばかり見ている場合ではありません。
高架下マップ(路線図)、鑑賞ポイント解説、高架下建築タイプ分け、おすすめ鑑賞コース、高架下建築考つき。
舞台となるのは、有楽町・新橋、アメ横、浅草橋、秋葉原、神田、国道、千住・三河島、向島、大井町、モトコー、三宮、御影、鶴橋、中津、大阪ぐるっと環状線。
いつも乗っているあの電車の下には、こんなに素敵な世界が広がっていた!鉄道好きな人たちも、上ばかり見ている場合ではありません。
高架下マップ(路線図)、鑑賞ポイント解説、高架下建築タイプ分け、おすすめ鑑賞コース、高架下建築考つき。
舞台となるのは、有楽町・新橋、アメ横、浅草橋、秋葉原、神田、国道、千住・三河島、向島、大井町、モトコー、三宮、御影、鶴橋、中津、大阪ぐるっと環状線。
- 本の長さ112ページ
- 言語日本語
- 出版社洋泉社
- 発売日2009/3/3
- ISBN-104862483844
- ISBN-13978-4862483843
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
商品の説明
著者について
大山顕(おおやま・けん)
1972年生まれ。高架下建築のほかにも、工場、団地、ジャンクション、などドボクなものに夢中。2004年から、ニフティの「デイリーポータルZ」での連載のほか、「工場鑑賞クルーズ」などさまざまな展覧会やトークショー、ツアーを主催。NHK-BS『熱中時間』のレギュラーも勤める。主な著書は「工場萌え」「団地の見究」(共に東京書籍)、「ジャンクション」(メディアファクトリー)など。
1972年生まれ。高架下建築のほかにも、工場、団地、ジャンクション、などドボクなものに夢中。2004年から、ニフティの「デイリーポータルZ」での連載のほか、「工場鑑賞クルーズ」などさまざまな展覧会やトークショー、ツアーを主催。NHK-BS『熱中時間』のレギュラーも勤める。主な著書は「工場萌え」「団地の見究」(共に東京書籍)、「ジャンクション」(メディアファクトリー)など。
登録情報
- 出版社 : 洋泉社 (2009/3/3)
- 発売日 : 2009/3/3
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 112ページ
- ISBN-10 : 4862483844
- ISBN-13 : 978-4862483843
- Amazon 売れ筋ランキング: - 697,796位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,348位写真家の本
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと発見したり、よく似た著者を見つけたり、著者のブログを読んだりしましょう
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2014年1月26日に日本でレビュー済み
まずもって下半分だけを写真にすることにより狭っ苦しさをアピールした表紙がオシャレ。中身も高架下建築の無法図さやコンパクトさを愛する著者の写真と文章が非常にいい感じです。
エリア的には阪神と首都圏の高架下建築を扱っていますが、雑然度は阪神が圧倒していると思います。ただ鶴橋や中津の迷宮ぶりは写真だけでは伝わりづらい部分もあるので、贅沢を言えば平面図もつけて欲しいところでした。
エリア的には阪神と首都圏の高架下建築を扱っていますが、雑然度は阪神が圧倒していると思います。ただ鶴橋や中津の迷宮ぶりは写真だけでは伝わりづらい部分もあるので、贅沢を言えば平面図もつけて欲しいところでした。
2009年7月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
高架下建築へのアプローチは、多彩な方面から出来ると思いますが、
私の場合は、その巧まざる芸術性に惚れ惚れします。
まず、無造作に塗り重ねられた壁のペンキが
まるでマーク・ロスコの絵画のよう。
そうしようと狙っているわけではない
無為の営みの中でできあがったものなので
あざとさがなく、ただ美しい。
そして、窓、ドア、郵便受けなどの方形のコンポジション。
絶妙の余白。
作品として狙って制作されたものでない美しさ。
巧まざる美という点では、工場の複雑かつ整然とした配管の美しさと通じるものがある。
(キレイなものを美しいとする一般的な美意識からすると、そうは感じない方が多いかもしれません)
これらの興味深い高架下建築写真を収集した作者に感謝。
しかし惜しむらくは、写真集としては本のサイズが小さい。
従って、写真も迫ってくる臨場感がやや足りなくなっているので
評価は星4つです。(でも被写体の面白さは星5つ)
林立するビルの裏側や
隣のビルが取り壊されて現れた
知られざるビルの側面の造作などに興味のある方にも
いいと思います。
私の場合は、その巧まざる芸術性に惚れ惚れします。
まず、無造作に塗り重ねられた壁のペンキが
まるでマーク・ロスコの絵画のよう。
そうしようと狙っているわけではない
無為の営みの中でできあがったものなので
あざとさがなく、ただ美しい。
そして、窓、ドア、郵便受けなどの方形のコンポジション。
絶妙の余白。
作品として狙って制作されたものでない美しさ。
巧まざる美という点では、工場の複雑かつ整然とした配管の美しさと通じるものがある。
(キレイなものを美しいとする一般的な美意識からすると、そうは感じない方が多いかもしれません)
これらの興味深い高架下建築写真を収集した作者に感謝。
しかし惜しむらくは、写真集としては本のサイズが小さい。
従って、写真も迫ってくる臨場感がやや足りなくなっているので
評価は星4つです。(でも被写体の面白さは星5つ)
林立するビルの裏側や
隣のビルが取り壊されて現れた
知られざるビルの側面の造作などに興味のある方にも
いいと思います。
2019年1月12日に日本でレビュー済み
高架下建築の醍醐味はその渾然一体としたところ。住宅系、倉庫系、店舗・事務所系・・。いちばん好きな高架下は神戸・元町エリアだけれども、今ではすっかり寂れてしまった。「どうやって生活してるんだろう?」「客なんて1日1人もこないだろ」という個人商店が並んでいたが、ひとつ、またひとつシャッターが降りたままの店舗が多くなり、閑散としている。ところどころ薄暗い箇所もあり女性のひとり歩きは怖いくらい。その元町高架下(モトコー)も掲載されているが、ページ数は多くない。・・耐震工事の名目でやがては取り壊される運命の高架下建築。「取り壊されたら上を向いて」というページが興味深いのでオススメ。
2012年5月18日に日本でレビュー済み
大山顕『高架下建築』(洋泉社、2009年)は高架下建築の写真集である。有楽町・新橋、アメ横、浅草橋、秋葉原、神田、千住・三河島、向島、大井町などを撮影した。高架下マップや鑑賞ポイントの解説もある。
著者は『工場萌え』(東京書籍)で知られる。工場という「萌え」とは対極のイメージがある建物に美を見出した。工場以外にも『団地の見究』(東京書籍)、『ジャンクション』(メディアファクトリー)など、マニアックな土木・建築分野を被写体として取り上げている。
『工場萌え』で取り上げられた工場には機能美やワイルドさがあった。これに対して『高架下建築』には雑然としたカオスが魅力である。生活や営業のコミュニティである高架下は、効率的な生産の場である工場とは別種の魅力がある。
鉄道高架下の建物は鉄道高架橋とは独立した構造を持ち、土地に定着し、周壁を有し、永続して建物の用に供することができる。所有権や賃貸借の対象になり、不動産登記も可能である。高架下の建物は高架下に暮らす人々の生活や営業の基盤であり、コミュニティがある。
高架下には近現代の歴史が詰まっている。『「ガード下」の誕生』では高架下を「大都会の歴史と発展の生き証人」とまで位置づける。ある修士論文でも望ましい高架下空間の利用法の一つが「記憶を残す装置」であると指摘された(平山隆太郎「鉄道高架下空間に対する住民の意識に関する研究」早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻景観・デザイン研究室2007年度修士論文、2008年2月8日)。
鉄道は公共性の高い事業である一方で、沿線住民にとっては線路が街を分断し、騒音・振動の被害もあるという迷惑施設の側面もある。その鉄道のマイナス面も補い、共存共栄する形で発展してきたものが高架下である。しかし、残念なことに鉄道会社の側から高架下のコミュニティを破壊する動きがある。
東京都品川区の東急大井町線高架下では東急電鉄によって住民や商店が立ち退きを迫られている。東急電鉄は住民の生活を保障せずに追い出しを図っている。東急電鉄は耐震補強を名目に立ち退きを迫るが、耐震補強工事中の仮住宅・仮店舗の手配も工事後の住民の期間も保証しない。『高架下建築』のような高架下の魅力を伝える書籍を歓迎する。(林田力)
著者は『工場萌え』(東京書籍)で知られる。工場という「萌え」とは対極のイメージがある建物に美を見出した。工場以外にも『団地の見究』(東京書籍)、『ジャンクション』(メディアファクトリー)など、マニアックな土木・建築分野を被写体として取り上げている。
『工場萌え』で取り上げられた工場には機能美やワイルドさがあった。これに対して『高架下建築』には雑然としたカオスが魅力である。生活や営業のコミュニティである高架下は、効率的な生産の場である工場とは別種の魅力がある。
鉄道高架下の建物は鉄道高架橋とは独立した構造を持ち、土地に定着し、周壁を有し、永続して建物の用に供することができる。所有権や賃貸借の対象になり、不動産登記も可能である。高架下の建物は高架下に暮らす人々の生活や営業の基盤であり、コミュニティがある。
高架下には近現代の歴史が詰まっている。『「ガード下」の誕生』では高架下を「大都会の歴史と発展の生き証人」とまで位置づける。ある修士論文でも望ましい高架下空間の利用法の一つが「記憶を残す装置」であると指摘された(平山隆太郎「鉄道高架下空間に対する住民の意識に関する研究」早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻景観・デザイン研究室2007年度修士論文、2008年2月8日)。
鉄道は公共性の高い事業である一方で、沿線住民にとっては線路が街を分断し、騒音・振動の被害もあるという迷惑施設の側面もある。その鉄道のマイナス面も補い、共存共栄する形で発展してきたものが高架下である。しかし、残念なことに鉄道会社の側から高架下のコミュニティを破壊する動きがある。
東京都品川区の東急大井町線高架下では東急電鉄によって住民や商店が立ち退きを迫られている。東急電鉄は住民の生活を保障せずに追い出しを図っている。東急電鉄は耐震補強を名目に立ち退きを迫るが、耐震補強工事中の仮住宅・仮店舗の手配も工事後の住民の期間も保証しない。『高架下建築』のような高架下の魅力を伝える書籍を歓迎する。(林田力)
2009年6月11日に日本でレビュー済み
とはいえ、全体的にキレイにまとまっている。
(文化財的なクオリティの高くない)下町とかの風俗的な写真を好む人から評価をえれそうなイイ意味で出来上がっている作品。
(文化財的なクオリティの高くない)下町とかの風俗的な写真を好む人から評価をえれそうなイイ意味で出来上がっている作品。