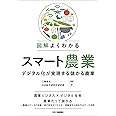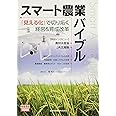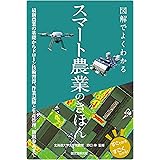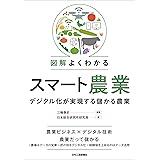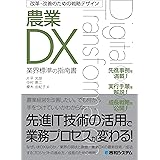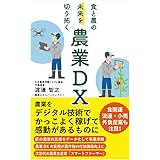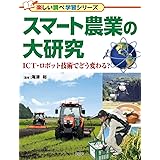農業にデジタルツールがほとんど入っていなかった時代から、農業現場に入り、農家さんとともに、開発をしてきた著者。
単なる効率化ではなく、現場で問題になるヒューマンエラーの削減にどう寄与すべきか考えたり、柔軟な対応をしていることが素晴らしいです。
また、その後も政府のデータ連携や、流通も含めた連携事業など、取組や構想を拡大されているのが興味深いです。
これを読めば、スマート農業の全体像と現在地がよく分かります。
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

スマート農業のすすめ~次世代農業人【スマートファーマー】の心得~ 単行本 – 2018/5/8
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥1,980","priceAmount":1980.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1,980","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"J%2FK1TMxxhiK97mgERbEXMwQaC%2FK3i7OgotbRuHk3%2FA0Dq4vfqqBgeq14bUYdY7j5if7kZZ5tLwVErutis7BO043ygDRWfAVls53OAjVKLrJ%2FYdlXlUfgfBomGA8%2BlMifzjVUBSembEU%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}
購入オプションとあわせ買い
【目次】
『はじめに』
1章 日本の農業のめざすべき姿とは
1.1 社会的背景
1.2 異業種参入・6次産業化の実態
1.3 輸出拡大
1.4 アメリカ合衆国のTPP離脱
1.5 GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)認証取得拡大
1.6 これからの農業協同組合との関わり
1.7 安心・安全とは
1.8 メイド・バイ・ジャパニーズ(Made by Japanese)と日式農法
1.9 農業における規模の経済
1.10 農業生産者を取り巻くプレイヤー
1.11 比較されるオランダ農業
1.12 少量多品種生産
1.13 イノベーター不足
2章 「スマート農業」の夜明け
2.1 農業現場の課題解決には「よそ者、若者、馬鹿者」が必要
2.2 自然環境ではなく、ヒューマンエラーが命取りに
2.3 農業組織としての「経営理念・事業ビジョン」について
2.4 農業生産者の五感の「見える化」
2.5 作業日誌の共有
2.6 農業生産におけるコスト
2.7 匠の農業のノウハウ
2.8 地域活性化・地方創生
3章 「スマート農業」普及に向けた政府の取り組み
3.1 農業分野における情報科学の活用に係る研究会(2009年度)
3.2 アグリプラットフォームコンソーシアム(2010年度~)
3.3 農業分野におけるIT利活用に関する意識・意向調査(2012年農林水産省)
3.4 「日本再興戦略」&「世界最先端IT国家創造宣言」(2013年)
3.5 スマート農業の実現に向けた研究会(2013年農林水産省)
3.6 農林水産分野におけるIT利活用推進調査(2014年農林水産省)&農業情報(データ)の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化に関する調査(2014年総務省)
3.7 革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究)(2014年~2017年)
3.8 クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立(2014年度)
3.9 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)(2014年~)
3.10 農業情報創成・流通促進戦略(2014年6月)
3.11 知的財産戦略(2015.5 農林水産省)&農業IT知的財産活用ガイドライン(農林水産省:慶應義塾大学委託)
3.12 「知」の集積と活用の場(2015年~)
3.13 農業経営におけるデータ利用に係る調査(2016年度)
3.14 農業データ連携基盤協議会(WAGRI)設立(2017年度)
4章 「スマート農業」が農業を魅力ある職業へ
4.1 「スマート農業」の現在位置
4.2 農業生産組織の大規模化
4.3 農業法人の実態
5章 匠(たくみ)の知識の形式知化に向けて
5.1 情報武装によるリスクヘッジ・ステークホルダー間でのリスクテイク
5.2 各種シミュレーション
5.3 匠の技術(ノウハウ、ナレッジ、こだわり)継承
5.4 ブランド、フランチャイズ化
5.5 「知的財産」が農業生産者の新たな収益源に
5.6 非破壊センシング、クオリティの担保
5.7 選果データと生産管理データの融合
5.8 画像解析技術の進歩と病害虫対策
5.9 盗難、人災、犯罪
5.10 衛星活用・リモートセンシング
5.11 ロボット・ドローン・アシストスーツ
5.12 遠隔農法
5.13 スマート農産物
6章 次世代農業を担う人材育成
6.1 “かっこよく"“感動があり"“稼げる"「新3K農業」の実現
6.2 農業生産者のキャリア形成
6.3 「スマートファーマー」の育成
6.4 「アグリデータサイエンティスト」の育成
6.5 「スマートアグリエバンジェリスト」の育成
7章 フードバリューチェーン外でのニーズ
7.1 金融、保険業でのICT 活用(アグリテック×フィンテック)
7.2 種苗メーカ
7.3 農業機械メーカでは
7.4 農地バンク(農地中間管理機構)では
8章 次世代食・農情報流通基盤(プラットフォーム)【Nober】構築
8.1 Noberの想定機能
8.2 農業生産者と消費者のニーズをマッチング
8.3 次世代のトレーサビリティ
8.4 次世代バイヤー(プリンシパルバイヤー)の必要性
8.5 食品・農業関連のオープンデータ&ビッグデータ
8.6 知られざる野菜の流通上での規格、食品ロス(フードロス)
8.7 ローカルロジスティクスの実現
8.8 健康や防災などその他分野とのデータ連携(医福食農連携)
8.9 バイオテクノロジーとの融合
8.10 再生可能エネルギーとスマート農業
8.11 スマートアグリタウンについて
『さいごに』
『はじめに』
1章 日本の農業のめざすべき姿とは
1.1 社会的背景
1.2 異業種参入・6次産業化の実態
1.3 輸出拡大
1.4 アメリカ合衆国のTPP離脱
1.5 GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)認証取得拡大
1.6 これからの農業協同組合との関わり
1.7 安心・安全とは
1.8 メイド・バイ・ジャパニーズ(Made by Japanese)と日式農法
1.9 農業における規模の経済
1.10 農業生産者を取り巻くプレイヤー
1.11 比較されるオランダ農業
1.12 少量多品種生産
1.13 イノベーター不足
2章 「スマート農業」の夜明け
2.1 農業現場の課題解決には「よそ者、若者、馬鹿者」が必要
2.2 自然環境ではなく、ヒューマンエラーが命取りに
2.3 農業組織としての「経営理念・事業ビジョン」について
2.4 農業生産者の五感の「見える化」
2.5 作業日誌の共有
2.6 農業生産におけるコスト
2.7 匠の農業のノウハウ
2.8 地域活性化・地方創生
3章 「スマート農業」普及に向けた政府の取り組み
3.1 農業分野における情報科学の活用に係る研究会(2009年度)
3.2 アグリプラットフォームコンソーシアム(2010年度~)
3.3 農業分野におけるIT利活用に関する意識・意向調査(2012年農林水産省)
3.4 「日本再興戦略」&「世界最先端IT国家創造宣言」(2013年)
3.5 スマート農業の実現に向けた研究会(2013年農林水産省)
3.6 農林水産分野におけるIT利活用推進調査(2014年農林水産省)&農業情報(データ)の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化に関する調査(2014年総務省)
3.7 革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究)(2014年~2017年)
3.8 クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立(2014年度)
3.9 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)(2014年~)
3.10 農業情報創成・流通促進戦略(2014年6月)
3.11 知的財産戦略(2015.5 農林水産省)&農業IT知的財産活用ガイドライン(農林水産省:慶應義塾大学委託)
3.12 「知」の集積と活用の場(2015年~)
3.13 農業経営におけるデータ利用に係る調査(2016年度)
3.14 農業データ連携基盤協議会(WAGRI)設立(2017年度)
4章 「スマート農業」が農業を魅力ある職業へ
4.1 「スマート農業」の現在位置
4.2 農業生産組織の大規模化
4.3 農業法人の実態
5章 匠(たくみ)の知識の形式知化に向けて
5.1 情報武装によるリスクヘッジ・ステークホルダー間でのリスクテイク
5.2 各種シミュレーション
5.3 匠の技術(ノウハウ、ナレッジ、こだわり)継承
5.4 ブランド、フランチャイズ化
5.5 「知的財産」が農業生産者の新たな収益源に
5.6 非破壊センシング、クオリティの担保
5.7 選果データと生産管理データの融合
5.8 画像解析技術の進歩と病害虫対策
5.9 盗難、人災、犯罪
5.10 衛星活用・リモートセンシング
5.11 ロボット・ドローン・アシストスーツ
5.12 遠隔農法
5.13 スマート農産物
6章 次世代農業を担う人材育成
6.1 “かっこよく"“感動があり"“稼げる"「新3K農業」の実現
6.2 農業生産者のキャリア形成
6.3 「スマートファーマー」の育成
6.4 「アグリデータサイエンティスト」の育成
6.5 「スマートアグリエバンジェリスト」の育成
7章 フードバリューチェーン外でのニーズ
7.1 金融、保険業でのICT 活用(アグリテック×フィンテック)
7.2 種苗メーカ
7.3 農業機械メーカでは
7.4 農地バンク(農地中間管理機構)では
8章 次世代食・農情報流通基盤(プラットフォーム)【Nober】構築
8.1 Noberの想定機能
8.2 農業生産者と消費者のニーズをマッチング
8.3 次世代のトレーサビリティ
8.4 次世代バイヤー(プリンシパルバイヤー)の必要性
8.5 食品・農業関連のオープンデータ&ビッグデータ
8.6 知られざる野菜の流通上での規格、食品ロス(フードロス)
8.7 ローカルロジスティクスの実現
8.8 健康や防災などその他分野とのデータ連携(医福食農連携)
8.9 バイオテクノロジーとの融合
8.10 再生可能エネルギーとスマート農業
8.11 スマートアグリタウンについて
『さいごに』
- 本の長さ180ページ
- 言語日本語
- 出版社産業開発機構
- 発売日2018/5/8
- 寸法14.8 x 1.3 x 21 cm
- ISBN-104860282949
- ISBN-13978-4860282943
よく一緒に購入されている商品
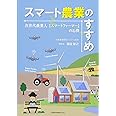
対象商品: スマート農業のすすめ~次世代農業人【スマートファーマー】の心得~
¥1,980¥1,980
最短で4月21日 日曜日のお届け予定です
残り1点(入荷予定あり)
¥2,200¥2,200
最短で4月21日 日曜日のお届け予定です
残り12点(入荷予定あり)
¥2,750¥2,750
最短で4月21日 日曜日のお届け予定です
残り1点(入荷予定あり)
総額:
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
商品の説明
著者について
渡邊 智之(わたなべ ともゆき)
日本農業情報システム協会 理事長
1993年富士通株式会社入社。
宅内交換機、宅内電話機の開発に従事、その後事業企画部門へ異動し、
医療・動物医療・農業に関するイノベーション創造に関与。「スマート農業ソリューション」の開発を主導。
2012年より、農林水産省において農林水産現場の情報化推進担当。
2014年に、ICTやIoT、AIなど「スマート農業」の利活用促進、人材の育成を目的とした
「日本農業情報システム協会(JAISA)」を設立し、同協会の理事長を務める。
農林水産業をICTで支援し、安心・安全で高付加価値な農林水産物の物流などにより、イノベーションを起こし、
さらには新たな職業や新たな雇用を生むことで、地域の活性化や地方創生に貢献することを生業としている。
日本農業情報システム協会 理事長
1993年富士通株式会社入社。
宅内交換機、宅内電話機の開発に従事、その後事業企画部門へ異動し、
医療・動物医療・農業に関するイノベーション創造に関与。「スマート農業ソリューション」の開発を主導。
2012年より、農林水産省において農林水産現場の情報化推進担当。
2014年に、ICTやIoT、AIなど「スマート農業」の利活用促進、人材の育成を目的とした
「日本農業情報システム協会(JAISA)」を設立し、同協会の理事長を務める。
農林水産業をICTで支援し、安心・安全で高付加価値な農林水産物の物流などにより、イノベーションを起こし、
さらには新たな職業や新たな雇用を生むことで、地域の活性化や地方創生に貢献することを生業としている。
登録情報
- 出版社 : 産業開発機構 (2018/5/8)
- 発売日 : 2018/5/8
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 180ページ
- ISBN-10 : 4860282949
- ISBN-13 : 978-4860282943
- 寸法 : 14.8 x 1.3 x 21 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 450,802位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 142位農学一般関連書籍
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

一般社団法人日本農業情報システム協会(JAISA)代表理事、スマートアグリコンサルタンツ合同会社(SAC) 代表/CEO、総務省 地域情報化アドバイザー。大手IT企業に入社し、主に各種センサーによる生育関連データ蓄積及び作業記録アプリ等の開発を主導しつつ、農業法人に飛び込み農業を学ぶ。その後農林水産省でスマート農業/農業DX推進担当として、政府のスマート農業/農業DX関連戦略策定や現場の普及促進に努める。慶應義塾大学SFC研究所の研究員や、農林水産省や自治体のスマート農業/農業DXに関する会議の有識者、座長としても参画している。
イメージ付きのレビュー
5 星
これからの農業ならびにあり方(事例)について書かれてます。
・スマート農業= ロボット技術やICT等の先端技術の活用による新たな農業。・ これまで経験と勘で行われてきた農業に限界が訪れると同時に、未曾有の課題(農業生産者数の減少ならびに高齢化など)が農業生産者に降りかかってきている。・現在の農業の環境ならびに体制が変わっていかなければ、日本における農業イノベーションが起きないと筆者は考えている。・本書では、筆者がスマート農業の企画立案をした経験で得たこと、スマートファーマー(スマート農業のスキルを持った農業生産者)が巣立つまでの事例が書かれている。・農業現場の課題解決には、「よそ者、若者、馬鹿者」が必要。農業にかかわったことがない異業種の人間が農業現場の実作業に少しかかわりあうだけで、多くの改善点を見出すことができる。・ロボット農業機械は劇的な進化を遂げている。本書が刊行された2018年、「栽培見回りロボット」「自立収穫台車ロボット」の開発に成功している。・ドローンを農業に活用している。主に使われるシーンとしては、農薬の散布、害虫の駆除、マルチスペクトルカメラを使ったリモートセンシング(センサーでの観測)である。・ドローンの一番のメリット=プログラミングにより、人が制御をしなくても自動で飛んでいける点。そのため夜間でも作業ができ、農業生産者の作業効率向上に役立っている。・この他にも、日本の農業の目指すべき姿や、現在の課題、スマート農業の普及に向けた政府の取組、次世代の農業を担う人材育成の方法ならびにプラットフォームの構築にむけた取り組みなどが書かれている。
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2019年3月6日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
内容は良いけどKindleで読むのはしんどい。Kindleで文字の大きさが調整できない本、結構ありますよね。
2018年7月22日に日本でレビュー済み
筆者は、大手ICT企業→中央省庁→農業生産法人→スマート農業推進団体に籍を置き、数多くの篤農家とICTベンチャー企業とのコネクションを持つ、これ以上スマート農業の実際を知る人はいないであろう人。勃興期から現在に至るまで格闘してきた筆者が初めて筆を執った本であり興味津々で読み始めました。
報道のされ方やPRの結果なのか、要素技術と理想が先行して実像が見えにくくなったスマート農業の地平をリアルに誠実に描いた良書だと思います。
本文からいくつか引用するが、
①全体の5%程度の先駆者および異業種からの参入者が自分達の求める効果(こだわりの明文化)を出そうと必死にトライ&エラーを繰り返している段階であると思っています。また、これらの取り組みも“点”であり、産地や地域をカバーするような“面”の活動にまで至っていないのが実情だ。残り95%の農業生産者は、状況を眺めながら、早期成功モデルの構築を期待して待っているというのが現状ではないだろうか(p.68)。
②農業に関するデータは、環境や土壌に大きく左右され、条件のまったく違うエリアの情報同士を融合させることが逆に真実から遠ざけることにつながるのである。要するに、北海道から沖縄までの農業生産者の生産に関する各種データを一箇所に集め「農業ビックデータ」として分析し、日本標準モデルを作ってもエリアが広すぎてしまい結果的にどこの地域に当てはまらないモデルになってしまうのである。(p.88)
③農業生産者が高品質な農業生産物を生産するためには、環境、種苗、生育、在庫、市況、人材、農機など、全方位のあらゆる完成やスキルが求められ、多くの知識と経験が必要とされる。その状況にもかかわらず、日本における農業という職業のプレゼンスが低すぎると筆者は感じている。農業は体力だけでなく知力も重要であり、様々なことを代表者一人で判断しなければならないことが多い。-中略―IotやAIといった最先端技術を駆使し、PDCAを繰り返し、さらにはそれを明文化し、最小リスクとなる次の一手を判断できる次世代の農業生産者(スマートファーマー)の存在が必要になってきているのである。(pp.131-132)
上記のような状況が現実なのだ。
矢継ぎ早にかわるトピックは、読みにくさもある。しかし、スマート農業自体が様々な分野で「事業検証」に入った段階であり、一般化・体系化・社会実装されていない様子を如実に表しているようにも思います。
年月と多様な実体験から洞察された、人・ICT企業・社会それぞれに対する指針をきちんと示しており、興味を持ち始めた人からスマート農業をめぐる全てのプレイヤーに必要な書だと思います。
又、中央省庁の調査やガイドライン、指針をまとめた、3章は今後のスマート農業をめぐる流れを占う上でも非常に重要と感じました。
報道のされ方やPRの結果なのか、要素技術と理想が先行して実像が見えにくくなったスマート農業の地平をリアルに誠実に描いた良書だと思います。
本文からいくつか引用するが、
①全体の5%程度の先駆者および異業種からの参入者が自分達の求める効果(こだわりの明文化)を出そうと必死にトライ&エラーを繰り返している段階であると思っています。また、これらの取り組みも“点”であり、産地や地域をカバーするような“面”の活動にまで至っていないのが実情だ。残り95%の農業生産者は、状況を眺めながら、早期成功モデルの構築を期待して待っているというのが現状ではないだろうか(p.68)。
②農業に関するデータは、環境や土壌に大きく左右され、条件のまったく違うエリアの情報同士を融合させることが逆に真実から遠ざけることにつながるのである。要するに、北海道から沖縄までの農業生産者の生産に関する各種データを一箇所に集め「農業ビックデータ」として分析し、日本標準モデルを作ってもエリアが広すぎてしまい結果的にどこの地域に当てはまらないモデルになってしまうのである。(p.88)
③農業生産者が高品質な農業生産物を生産するためには、環境、種苗、生育、在庫、市況、人材、農機など、全方位のあらゆる完成やスキルが求められ、多くの知識と経験が必要とされる。その状況にもかかわらず、日本における農業という職業のプレゼンスが低すぎると筆者は感じている。農業は体力だけでなく知力も重要であり、様々なことを代表者一人で判断しなければならないことが多い。-中略―IotやAIといった最先端技術を駆使し、PDCAを繰り返し、さらにはそれを明文化し、最小リスクとなる次の一手を判断できる次世代の農業生産者(スマートファーマー)の存在が必要になってきているのである。(pp.131-132)
上記のような状況が現実なのだ。
矢継ぎ早にかわるトピックは、読みにくさもある。しかし、スマート農業自体が様々な分野で「事業検証」に入った段階であり、一般化・体系化・社会実装されていない様子を如実に表しているようにも思います。
年月と多様な実体験から洞察された、人・ICT企業・社会それぞれに対する指針をきちんと示しており、興味を持ち始めた人からスマート農業をめぐる全てのプレイヤーに必要な書だと思います。
又、中央省庁の調査やガイドライン、指針をまとめた、3章は今後のスマート農業をめぐる流れを占う上でも非常に重要と感じました。
2020年12月13日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
気にいらなかった
2021年5月19日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
スマート農業とはなんなのか、聞き慣れない言葉が気になって購入しました。農業の事がまるでわからない読者にも丁寧でわかりやすい文章で、読み終わる頃には日本の農業について少し詳しくなった気持ちになり、特に、フードロスの項目については、とても興味深く読ませていただきました。
2021年10月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
IT化の歴史や政策の話が多く、つまらなくて全部は読めませんでした。どうすればどういう事ができるかHowTo的なものが欲しい。
2021年10月21日に日本でレビュー済み
スマート農業に興味があり、検索で出てきたこちらを読みました(Amazon購入ではないです)。
良い点
○様々な取り組みが紹介されている。
○政府の取り組みや会社の取り組みなど幅広い立場から書かれている。そういう視点からも考えることができるのか!と気づける。
○農業のことをほとんど知らなかったので、スマート農業以前に農業の問題点がわかる。
悪い点
○カタカナ語が多くすんなり文が入ってこない。
○文の誤字が多い(私が呼んだのは初版なので、もう直っているかもしれませんが)。
○著者の個人的な考えというが、これが比較的一般的なものなのか、そうでないのかが初心者にはわからない。
○同じ話が多い。1章ごとにどこかの雑誌に寄稿したものをまとめた本ならともかくそうではなさそう。
○抽象的な表現になるが、なんとなく偉そう、机上の空論な感じを受けた。
良い点
○様々な取り組みが紹介されている。
○政府の取り組みや会社の取り組みなど幅広い立場から書かれている。そういう視点からも考えることができるのか!と気づける。
○農業のことをほとんど知らなかったので、スマート農業以前に農業の問題点がわかる。
悪い点
○カタカナ語が多くすんなり文が入ってこない。
○文の誤字が多い(私が呼んだのは初版なので、もう直っているかもしれませんが)。
○著者の個人的な考えというが、これが比較的一般的なものなのか、そうでないのかが初心者にはわからない。
○同じ話が多い。1章ごとにどこかの雑誌に寄稿したものをまとめた本ならともかくそうではなさそう。
○抽象的な表現になるが、なんとなく偉そう、机上の空論な感じを受けた。
2018年5月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
農業を汚い、きつい、カッコ悪いの3Kから、稼げる、感動、かっこ良いの新3Kへ‼
若い人も就農したくなるスマート農業のノウハウが身近に学べる本にはじめて出合いました。
図解も絵も分かり易くITに詳しくない私も惹きこまれました。
お勧めの1冊です!
若い人も就農したくなるスマート農業のノウハウが身近に学べる本にはじめて出合いました。
図解も絵も分かり易くITに詳しくない私も惹きこまれました。
お勧めの1冊です!