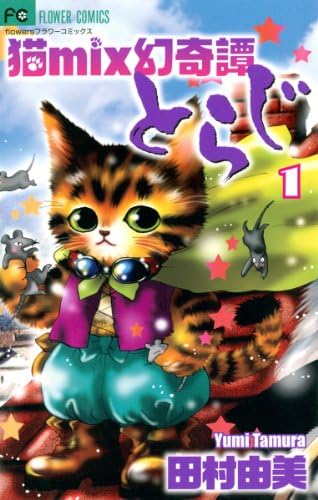| 獲得予定ポイント: | +15 pt (1%) |
これらのプロモーションはこの商品に適用されます:
一部のプロモーションは他のセールと組み合わせることができますが、それ以外のプロモーションは組み合わせることはできません。詳細については、これらのプロモーションに関連する規約をご覧ください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

米ビジネス Kindle版
・なぜコシヒカリは日本一有名なお米になったのか
・産地によってコシヒカリの味は違うのか
・なぜ無洗米は洗わなくてもいいのか
・精米で変わるお米の栄養価と味
・「JA米」は他のお米と何が違うのか
・お米の値段はどうやって決まるのか
・牛丼チェーン店のお米ができるまで
・稲作の最新テクノロジー
・驚きの進化を遂げるパックライス
など、明日から使える雑学やビジネスの専門知識まで幅広く網羅。誰でも楽しく読める1冊です。
著者は横浜にある老舗米屋の3代目で、自身も「米・食味鑑定士」として数多くの品評会に参加し、全国の米農家を渡り歩いた米のプロ・芦垣裕氏です。
この本を読めば、日本人として生まれた誇りが芽生えてくること間違いなしです。
- 言語日本語
- 出版社クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日2024/9/13
- ファイルサイズ3.2 MB
出版社より


なぜ「コシヒカリ」は有名になったのか
第二次世界大戦後、食糧難を乗り越え高度経済成長期を迎えた日本では、収穫量が多く味の美味しかったコシヒカリが新潟県と千葉県で1956年に奨励品種として採用されました。
その当時は、葉や根が枯れ「イネの疫病」ともいわれるいもち病に弱い点や、倒れやすい点といった課題がありましたが、栽培方法の研究と生産者のノウハウ構築が進み、安定的に美味しく作れるようになりました。さらに、1962年に新潟県で「日本一うまい米づくり運動」が展開され、コシヒカリに代表される食味の良い品種の1等米に「新潟米」と書かれた赤票箋を付けることで、品質保証を推進したのです。

なぜ「ゆめぴりか」は北海道産にしかないのか
北海道は他の都府県より気温も低く、日照時間も短いという特徴があります。一方で、お米を実らせる稲は元々南の地域で作られ、寒さに弱いものがほとんどです。
しかし近年は地球の温暖化によって、北海道での米生産も行われ、研究者や生産者の努力でブランド米が徐々に誕生しはじめています。 その中で「ゆめぴりか」はブランド戦略として、「新潟県産コシヒカリを超えるブランド力をつけ、食味もそれ以上を目指す」という方針があり、良質な種籾の選別から生育までを一貫して行なっています。 こうした状況が「ゆめぴりか」の特別感を上げ、ブランド力の向上にもつながっています。

稲作のテクノロジー
種籾の発芽を促進させる技術や、より多く収穫できる品種への改良といったバイオテクノロジー技術の発展は目覚ましいものがあります。 栽培技術そのものでは、種籾が浮かないように鉄でコーティング処理をし、ドローンを使って種のまま田んぼに撒くという「鉄コーティング直播栽培」といった技術も開発されています。こうすることで、重たい苗を運ぶ必要もなくなり、田植えの労力を最小限に抑えることができます。
これらの技術には、自動運転トラクターのように導入が進んでいるものもありますし、ICT技術のように費用が掛かるなどの理由で導入が進んでいないものもあります。

なぜ無洗米は洗わなくて良いのか
無洗米とは、お米を研いだり洗ったりしなくても水を加えるだけで炊飯できるように加工したお米のことです。このようにできるのは、精米後のお米の表面に付いている肌糠まで取り除いているからです。
今や無洗米の技術も進歩を遂げ、最新鋭の工場では、精米度合いの低い「分づき米」や「胚芽米」でも無洗米に加工できるようになりました。 ちなみに、無洗米が登場したのは1991年と言われています。

JA米は何が違うのか
現在ではお米の流通は自由化されていますが、1995年以前はお米の流通が政府によって管理されていたこともあり、その大半がJAを経ていました。そのような歴史もあるので、JAの流通への影響力は大きいものがあります。
農協協会がまとめた2022年のコメ実態調査によると、JAの米集荷率は全国平均で53 %となっており、特に北海道は82 %、東日本は60 %と多くなっています。 JAによると、お米の全国の均一化、画一化を目的とするのではなく、各産地の個性あるお米づくりをサポートする土台づくりを目指すのがJA米の位置づけとしています。

売れ残ったお米はどうなるのか
お米は、籾や玄米の状態で保管されていれば、低温倉庫などで長期保管ができるので、比較的余裕を持って販売計画が立てられます。そのため、この場合はどこかしらの売り先に行き着きやすいところがあります。 問題は、精米後の白米です。 お米は精米してしまうと、販売できるレベルの品質が保持しにくくなります。品質が保てても、せいぜい1ヶ月程でしょう。

研ぎ方で変わるご飯の味
この研ぐ回数によって、ご飯の味はビックリするほど変わってしまいます。 私の経験では、「つや姫」を3回研いだ時には甘みと香りが良いご飯になりましたが、4回研ぐと「ひとめぼれ」のようなさっぱりした甘味のご飯になりました。粘りの強いお米であっても研ぎ方を強くすると、あっさりした感じになります。
また、季節によっても研ぎ方を変えると、お米の美味しさも変わってきます。 新米が出てから翌年の1月中旬ぐらいまでは、お米の水分が保たれていることが多くて柔らかいので、研ぐ際に力を入れすぎるとお米が割れて美味しくなくなります。

牛丼チェーン店のご飯ができるまで
牛丼大手3社である「吉野家」「松屋」「すき家」では、最近はあまり単一品種を使わず、ブレンド米が増えてきているようです。そうすることで、安定した美味しさを提供できるというメリットがあります。大手のうち1社は、常に10 種類前後の品種をストックしているようですし、どの会社もブレンド技術にはとても高いものがあります。
また、お米も農協や米卸会社だけでなく、生産者からも直接仕入れたりしています。これは、お米がどのようにして流通してきたか、トレーサビリティ(製品がいつ、どこで、誰によって作られたか)を明らかにするための取り組みでもあります。

驚きの進化を遂げるパックライス
パックライスの正式な名称は、「包装米飯」と言います。さらに、包装米飯には炊飯前のお米を殺菌して炊いてから無菌包装した「無菌包装米飯」と、包装後に加圧加熱殺菌した「レトルト米飯」の2つの製法があります。
2つの違いをわかりやすく記すと、「加熱→包装」が無菌包装米飯で、「包装→加熱」がレトルト米飯となり、原理的には順番が違うだけです。ただ、この順番の違いが性質にも違いを生みます。

魚ビジネス
|

肉ビジネス
|

野菜ビジネス
|

米ビジネス
|

酒ビジネス
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1 162
|
5つ星のうち4.0 41
|
5つ星のうち3.8 17
|
5つ星のうち3.7 17
|
5つ星のうち4.4 17
|
| 価格 | ¥1,738¥1,738 | ¥1,738¥1,738 | ¥1,738¥1,738 | ¥1,738¥1,738 | ¥1,738¥1,738 |
| 業界シリーズ | 「美味しい寿司屋を知っていると尊敬されます。」日本テレビ系ドラマ「ファーストペンギン!」の漁業監修も手がけた著者による「魚の入門書」。魚にまつわるビジネスから、寿司の歴史、市場で美味しく魚を食べる方法、培養魚肉の最新技術など、明日から使える豆知識をご紹介。 | 「美味しい焼肉屋を知っていると人気者になれます。」年間300日和牛を食べる「肉バカ」が教える、「肉の教養」。肉にまつわるビジネスの話から、肉産業の歴史、肉の美味しさを決める要素の解明、焼肉の味わい方、海外で評価される和牛の魅力など、明日からすぐに使える豆知識を紹介する「和牛の入門書」です。 | 「野菜ジュースで1日分の野菜は摂れるのか」野菜の可能性を探究し続ける野菜研究家が教える「野菜の教養書」。野菜にまつわるビジネスの話から、野菜の歴史、産直野菜、加工野菜、お取り寄せ野菜、ファーム・トゥー・テーブル、美味しい食べ方など、明日からすぐに使える豆知識をご紹介。 | 【いつも食べているのに、実は知らないことばかり!?】『なぜコシヒカリは日本一有名なお米になったのか』鑑定士として、試食したお米は4000以上! 全国を渡り歩いたお米の目利きが教える「お米の教養書」明日から使える雑学やビジネスの専門知識まで幅広く網羅しています。 | 年間2000種類の日本酒を呑む酒蔵コーディネーターが教える「お酒の教養」。日本酒は国内に限らず、世界中で酒蔵が生まれる注目のジャンル。日本酒は今、「世界の教養」として世界各国から認識されはじめているのです。本書を読めば、ビジネスから日常の雑談まで、様々なシーンで日本酒について語れること間違いなしです。 |
商品の説明
著者について
有限会社初音屋 代表取締役
米・食味鑑定士/水田環境鑑定士/調理炊飯鑑定士/おこめアドバイザー
横浜で3代続く米屋の店主。取り扱うお米は、田んぼの自然環境までを自ら確認し、気に 入ったお米のみ。米・食味分析鑑定コンクール国際大会の審査員を20年以上務めている。 そのほか、お米日本一コンテストin静岡の全国大会、天栄米コンクール(福島県)、栃木 県産米食味鑑定コンクール、飛騨の美味しいお米食味コンクールなど、多数のお米コン クールの審査員を務める。また、ふるさと納税のポータルサイト「ふるさとチョイス」の お米特集をはじめ、フジテレビ「LiveNewsイット!」など、メディアでもお米に関する コメントを行い、お米の素晴らしさを伝えている。 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。
登録情報
- ASIN : B0DGWQ2TT1
- 出版社 : クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2024/9/13)
- 発売日 : 2024/9/13
- 言語 : 日本語
- ファイルサイズ : 3.2 MB
- Text-to-Speech(テキスト読み上げ機能) : 有効
- X-Ray : 有効にされていません
- Word Wise : 有効にされていません
- 本の長さ : 224ページ
- Amazon 売れ筋ランキング: - 183,023位Kindleストア (Kindleストアの売れ筋ランキングを見る)
- - 22,834位ビジネス・経済 (Kindleストア)
- カスタマーレビュー:
著者について

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
イメージ付きのレビュー
日々の食事が楽しくなる、ご飯が美味しくなる
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年11月18日に日本でレビュー済みAmazonで購入ほぼ毎日口にする身近なお米だからこそ知っておいた方がいい内容が知識のない私にも分かりやすく書かれていました。
パックライス等、更に便利になっていく今の時代だからこそ改めて知識を身につけても良いと思います。
- 2024年12月17日に日本でレビュー済み米農家です。作る以外の部分も網羅されていて勉強になります。
?は米の中の農薬が抜ける、抜け切らないとか、農薬によって雑草を除去しすぎて田んぼの養分が抜け切らないという表現。
これは科学的根拠を聞いたことがないです。
私の不勉強であったらごめんなさい。
- 2024年11月4日に日本でレビュー済みAmazonで購入お米は好き、違いもなんとなくはわかる気がする、そんなほとんどの日本人に読んでほしい一冊です。
お米への愛と知識が深まります。
- 2025年2月7日に日本でレビュー済み著者には申し訳ないけど、正直、薬にも毒にもならないクソつまらない本です。
文章は丁寧ですが、まるで農水省やJAの広報誌に掲載されている情報を並べたような本です。
素人さんには、少しは役立つかも知れないけど、素人さん以外には、全く役立ちません。
しかも、図説などは一切なし。
素人さん以外にはオススメできないです。
- 2024年10月15日に日本でレビュー済みAmazonで購入品種、農業から外食、これからのお米ビジネスのことまで、お米のことを網羅的に知ることができます。
ある程度お米のことは知っているため、知っていたことも書かれていましたが、それはそれでおさらいできたのでよかったです。
個人的には、品種の章や加工の章、外食・中食の章が特に面白く、パックライスや業務用炊飯システムなどの最新テクノロジーやお米事情には、「へぇ~」という感じでした。
確かに日々食べるものなので、お米のことを更に勉強することで、生活がもっと豊かになるように思いました。その入口としては最適な本で、お米のことをこれから学びたい人には特におすすめできる本です。
- 2024年9月25日に日本でレビュー済みAmazonで購入本書は、僕のような素人でも楽しく読めるように書かれ、まるでお米の博物館を見学しているような気になるお米に関する豆知識、生活に役立つヒントの宝庫です。まず開いて、予想以上に小さな字でびっしり、充実した内容になっているのに驚きました。
1章:米ビジネスの概要
2章:品種について
3章:稲作について
4章:加工について
5章:流通について
6章:小売について
7章:炊き方について
8章:外食とお弁当について
9章:お米のこれからについて
個人的な見解ですが、大まかに見て、お米は米単体として食べることを前提に「美味しいご飯」を追求した縦方向の発展と、加工の多様化といった横方向の展開があるように思います。前者の美味しいご飯の追求は、言えば淡白な穀物であるお米の繊細な味わいに深く拘る、それに付随して、美味しく炊けるお釜の開発も繊細な方向に拘っていく。結果として、それは日本の米食文化の特徴となっていくわけですが、そういう姿勢はこれからも失わないで欲しいなと思います。カレーに合うお米のブレンドとか、驚きました。
これまで全く知らなかったのですが、それぞれの品種に大まかな特徴がありつつも、気候、土壌、水、肥料、育て方などによって、同じ品種でも違った味わいのお米になってしまう。安定した品質を出すためにお米をブレンドすることもあれば、1農家で個性的なお米を生産することもある。品種によって、合うおかずも違ってくる。これらのような特徴は、まるでワインやウィスキーのようであり、お茶碗に盛られた見慣れた白いご飯にそれほどまでの繊細さ、奥深さがあろうとは思いもよりませんでした。こうしたことを知ると、これからのご飯の見え方が変わってきますし、ちょっとした気配りで日々の食事がもっと楽しくなっていくと思います。
 本書は、僕のような素人でも楽しく読めるように書かれ、まるでお米の博物館を見学しているような気になるお米に関する豆知識、生活に役立つヒントの宝庫です。まず開いて、予想以上に小さな字でびっしり、充実した内容になっているのに驚きました。
本書は、僕のような素人でも楽しく読めるように書かれ、まるでお米の博物館を見学しているような気になるお米に関する豆知識、生活に役立つヒントの宝庫です。まず開いて、予想以上に小さな字でびっしり、充実した内容になっているのに驚きました。
1章:米ビジネスの概要
2章:品種について
3章:稲作について
4章:加工について
5章:流通について
6章:小売について
7章:炊き方について
8章:外食とお弁当について
9章:お米のこれからについて
個人的な見解ですが、大まかに見て、お米は米単体として食べることを前提に「美味しいご飯」を追求した縦方向の発展と、加工の多様化といった横方向の展開があるように思います。前者の美味しいご飯の追求は、言えば淡白な穀物であるお米の繊細な味わいに深く拘る、それに付随して、美味しく炊けるお釜の開発も繊細な方向に拘っていく。結果として、それは日本の米食文化の特徴となっていくわけですが、そういう姿勢はこれからも失わないで欲しいなと思います。カレーに合うお米のブレンドとか、驚きました。
これまで全く知らなかったのですが、それぞれの品種に大まかな特徴がありつつも、気候、土壌、水、肥料、育て方などによって、同じ品種でも違った味わいのお米になってしまう。安定した品質を出すためにお米をブレンドすることもあれば、1農家で個性的なお米を生産することもある。品種によって、合うおかずも違ってくる。これらのような特徴は、まるでワインやウィスキーのようであり、お茶碗に盛られた見慣れた白いご飯にそれほどまでの繊細さ、奥深さがあろうとは思いもよりませんでした。こうしたことを知ると、これからのご飯の見え方が変わってきますし、ちょっとした気配りで日々の食事がもっと楽しくなっていくと思います。
このレビューの画像
- 2024年10月9日に日本でレビュー済み本当の初心者向けです。
平易な文章ですごく読みやすいのですが
米を深く追求したい場合にはちょっと物足りないです。知っていることばかりでした。
例えばぶづきまいの項目。ミネラルやビタミンなどの栄養素とかの比率をぶづきごとに表にしてあるかなと思ったが文章だけだった。
- 2024年12月19日に日本でレビュー済みお米の銘柄には特にこだわりなく、値段重視で食べていましたが、当たり前にあったお米が買えなくなり、この本を手に取りました。色々なお米の誕生秘話などが、まとめて読めて楽しかったです。これを機に色々なお米を食べてみたいとおもいました。他のお米の事や、今後の米ビジネスにも、注目したいと思います。