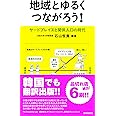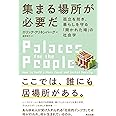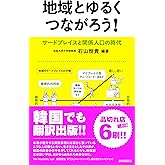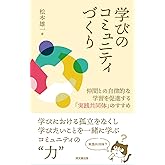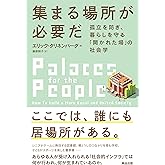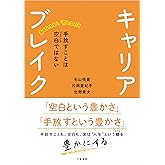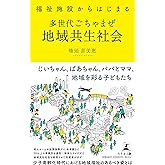この本を手に取った最大の理由は、私が長く暮らす街が事例に取り上げられていることです。この街
にそんなサードプレイスがあったんだという驚きをもって、読みはじめました。
本書をイキイキとしたものにしているのは、17のストーリーです。それらによって、無味乾燥な学術
書にならずに、もしかしたら自分も参加したり、さらには新しいコミュニティをつくれるかもしれな
いと前向きな気持ちになります。
とはいえ、本書の「軸」を示しているのは、法政大学の石山さん(教授)が書いている序章です。
サードプレイスが注目されるのは、「ゆるさ」と「小さな物語」だ
「ゆるさ」とは、強制されない自発性です。そして、「小さな物語」は、各人が自分の楽しさを
大切にしながら何人かで共通する目的を追求することです。
本書には、読み解くために欠かせない重要な図が2つ掲載されています。
そのうちの一つは、”図1:従来型の地域コミュニティとサードプレイスの比較” です。
縦軸に「目的」ー「癒し・憩い」、横軸に「自発的」ー「義務的」を取り、四象限を形成して、次の
ように定義しています。
目的 × 自発的:目的交流型(地域のサードプレイス)
… 地域のNPO、地域の勉強会や子ども食堂
目的 × 義務的:義務的共同体(従来型の地域コミュニティ)
… 自治会、町内会、PTA
癒し・憩い × 自発的:社交交流型(地元の居酒屋)/ マイプレイス型(チェーンコーヒー店)
癒し・憩い × 義務的: ー
こうやって図表化されるとみえてくるのは、サードプレイスのサードプレイスたる所以は、「自発
的」なものであることで、だから「楽しい」ことだとわかります。
逆に見るなら、従来型の地域コミュニティである「義務的共同体」は、実質上崩壊していることを
私たちは目の当たりにしています。やらされ感では、楽しくないからです。
また、共通の目的があって集まるから、さらに楽しんでワクワクできるうえに、地域への貢献にも
つながるため、やりがいを持つこともできます。
さらに言うなら、もうひとつの図で表されている ”図2:サードプレイスの拡張” では、場所に縛ら
れない空間性(テーマ性)と場所性(地域性)を縦軸に据えています。
石山さんが主張しているように、場所と空間は相補関係にあると考えることを現在のテクノロジー
は可能にしてくれています。この2つの「場」がびしっと嵌れば、地域課題の解決を越えた、社会
課題の解決へと拡張できるうえに、共通の興味・関心を持つ人との出会いの機会が増えます。
本書の主旨からはみ出てしまいますが、サードプレイスという世界観の拡張は、これからの大きな
テーマになるかもしれません。
冒頭に書いたように、本書を手に取ったきっかけは我が街のサードプレイスが紹介されていること
です。引っ込み思案な私ですが、来月に開催される我が街のイベントへの参加し、楽しんでこよう
と思っています。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ゆるい場をつくる人々: サードプレイスを生み出す17のストーリー 単行本(ソフトカバー) – 2024/9/15
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥2,640","priceAmount":2640.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"2,640","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"N70qDAFCqCzMDC2%2Bg3g58GDsXVhS88MDjnWKtq1mdGfn5nw47SM34OujX8fMI5tld01hVlXjfF6%2B8AHIkZUulY0jrZkHNYrVarCyaE6JwWfcmbnDERDGXGbDLHnY6QhTMjuNerDyNgI%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}
購入オプションとあわせ買い
コワーキングスペース・まちの学び舎・コミュニティ農園・シェア本屋・
女性やシニアの仕事場・減災/防災活動・医カフェ…
あるのは、人の数だけあるやりたいこと。
今「強制されない自発性=ゆるさ」が地域に、人に必要だ。出入り自由、フラットな関係、事務局が目立たない、楽しいから参加する、あるのは人の数だけあるやりたいこと。コワーキングスペースやまちの学び舎、コミュニティ農園、シェア本屋、女性やシニアの仕事場、減災・防災活動、医カフェなど、17のサードプレイスの物語
【目次】
■■序 ゆるい場としてのサードプレイス(石山恒貴)
1 ゆるさとは何か、なぜゆるい場が生まれるのか
2 ゆるい場の特徴と条件
3 ゆるい場をつくる人々
4 本書の4テーマ
■■1章 行きたい時に行ける場所
■事例1 「まちの非武装地帯」としてのコワーキングスペース──チガラボ|神奈川県茅ヶ崎市(石山恒貴)
1 まちの非武装地帯
2 理想のサードプレイスが存在した
3 ゆるい場をつくる人:清水謙さん──新しいことに1人で挑戦し続ける
4 チガラボという実験の始まり
5 交流×学習×実践のコミュニティ
6 まち自体が実験場になればいい
■事例2 まちの学校、コラーニングスペース──HLS弘前|青森県弘前市(石山恒貴)
1 まちの中でこそ実現する教育
2 ゆるい場をつくる人:辻正太さん──「ルイーダの酒場」(冒険する仲間を探す場所)をつくりたい
3 体育教師を目指した学生時代
4 中高一貫校の教師に
5 弘前で「ルイーダの酒場」を実現する
5 HLSの始動と成長
7 学校教育に戻る
■事例3 全員で運営するコモンズ農園──EdiblePark茅ヶ崎|神奈川県茅ヶ崎市(平田朗子)
1 会員制コミュニティ農園というチャレンジ
2 ゆるい場をつくる人:石井光さん──気さくな近所のお兄ちゃん
3 地主の13代目として辻堂で育つ
4 「巻き込まれ事故」のような流れで代表に
5 時間をかけて共存できるようになればいい
■事例4 みんなでみんなに大丈夫力をつける──サステナブルライフ研究会@湘南|神奈川県藤沢市(秋田志保)
1 有志のご近所メンバーでゆるく知識をシェアする会
2 住む人一人ひとりの安心感、大丈夫という感覚
3 ゆるい場をつくる人:齋藤佳太郎さん──生活用品の手作り実験から生まれたつながり
4 決めすぎない運営、選びすぎない人選
5 「軒先の未活用フルーツ」で湘南地域をつなげたい
■■2章 自分が行きたいと思える場所づくり
■事例5 十人十色、オトナたちのまちの学び舎──こすぎの大学|神奈川県川崎市(本多陽子・森隆広)
1 武蔵小杉に生まれた学び舎
2 ゆるい場をつくる人:岡本克彦さん──堅苦しくない伸び伸びとした居心地の良さ
3 会社以外の誰とも交流しない日常に気づいて
4 月1回、地域の懇親の場に新旧住民が集う
5 メンバーの思いはみんなバラバラ
6 住民の「やりたい」を後押しする、地域のハブ
■事例6 都心のコミュニティ菜園──そらとだいちの図書館|東京都新宿区(渡辺萌絵)
1 図書館の空地を活用したコミュニティ菜園
2 ゆるい場をつくる人:渡辺萌絵さん──場所も、資金も、人脈も、スキルも無い
3 自分にできる小さなことから──町内会長へ宛てた手紙とイラスト
4 空地を使った菜園イベント、多世代をつなぐ家族食堂、そして充電期間へ
5 ずっと気になっていた図書館の空地活用計画
6 試行錯誤しながら走り続ける
■事例7 イベント未満・カウンセリング未満の話せるシェア本屋──とまり木|神奈川県茅ヶ崎市(片岡亜紀子・谷口ちさ・平田朗子)
1 街に「リアルに話せる場所」を
2 とまり木に惹かれる理由
3 ゆるい場をつくる人:大西裕太さん──社会復帰から始まった場づくりの構想
4 みんなでつくるとまり木
5 訪問者が思い思いに過ごせる場所
■■3章 女性もシニアも心地よく働けるコミュニティ
■事例8 誰もが心地良く暮らし、働ける場をつくる──非営利型株式会社Polaris|東京都調布市(秋田志保・片岡亜紀子)
1 非営利型株式会社とは
2 ゆるい場をつくる人:市川望美さん──言葉と理念の人
3 誰もが自分で自分の働き方を選べるように
4 成長と拡大を経て感じた変化
5 生き方の選択肢を増やす
■事例9 シニアと仕事と地域をつなげる──NPO法人セカンドワーク協会|神奈川県茅ヶ崎市(小山田理佐・宮下容子)
1 シニアも現役世代も、共にセカンドワークを手に入れる
2 なぜNPO法人なのか──社会貢献活動への覚悟
3 ゆるい場をつくる人:四條邦夫さん──長年の会社員生活、起業、そしてNPO法人設立
4 試行錯誤した経験がつながっていく
5 仲間が増え、組織基盤を整えて活動の拡大を目指す
■事例10 「企業研修」をきっかけに会社員が地域にゆるく関わっていく──株式会社machimori|静岡県熱海市(佐々木梨華)
1 まちづくり会社が行う企業研修事業
2 ゆるい場をつくる人:佐々木梨華さん──machimoriの企業研修事業を立ち上げるまで
3 売るプログラムがない、顧客もいない、体制もない
4 machimoriの企業研修事業部のこれから
■■4章 楽しいから楽しい、地域活動
■事例11 富士山が微笑む若者のまちづくり── 一般社団法人F-design|静岡県富士市(石山恒貴)
1 若い世代が富士市を盛り上げる
2 個性が異なる3人の若者
3 ゆるい場をつくる人:大道和哉さん──F-designを立ち上げるまで
4 ゆるい場をつくる人:川上大樹さん──F-designに出会うまで
5 ゆるい場をつくる人:井出幸大さん──F-designに出会うまで
6 路線変更と信頼関係
7 社交交流型サードプレイスから、目的交流型サードプレイスへ
■事例12 人と農を結ぶ暮らしの創造──NPO法人湘南スタイル|神奈川県茅ヶ崎市(小山田理佐・近藤英明・佐藤雄一郎)
1 農業支援からはじまった湘南の老舗NPO法人
2 ゆるい場をつくる人:渡部健さん──農と食を通じて地域を盛り上げたい
3 やりたい人に任せる、緩いつながりの運営
5 街の人事部──住民が共に成長し支え合う
■事例13 楽しく備える新しい減災・防災のかたち──溝の口減災ガールズ|神奈川県川崎市(本多陽子)
1 減災・防災を「自分ごと」に
2 ゆるい場をつくる人:山本詩野さん──被災地へ支援に行ったつもりが、逆に刺激を受けて帰ってくる
3 近隣連携の副産物──「溝の口減災ガールズ」の誕生
5 マジメだけど軽やかに
6 できる時に、できるひとが、できることを
7 いざという時に手がつなげる安心感
■事例14 多様な関係人口とのつながりがまちを変える──ARUYO ODAWARA|神奈川県小田原市(大川朝子)
1 多様な関係人口が行き交う都市のコミュニティ
2 ゆるい場をつくる人:コアゼユウスケさん──人生は学校ではなく、すべてタワーレコードから教わった
4 住民・移住者・リモートワーカーが集まる場で好循環が生まれる
5 楽しく生きる大人を増やす
■事例15 面白そう、楽しそうでつながる里山のコミュニティ─ ──バー洋子・焚き火編集室|福岡県宗像市(北川佳寿美)
1 多彩な顔をもつデザイナー
2 ゆるい場をつくる人:谷口竜平さん──田舎での暮らしと、都会への屈折した憧れ
3 かっこいい大人とかっこいい仕事
4 「田舎はいい」が初めて腑に落ちた瞬間
5 一万坪の里山でゆるく地域とつながり続ける
■事例16 定年後に地域とゆるくつながる──ながはま森林マッチングセンター・星の馬WORKS・もりのもり|滋賀県長浜市(八代茂裕)
1 山を活かす、山を守る、山に暮らす
2 マッチングセンターとのゆるく心地よい関係
3 ゆるい場をつくる人:橋本勘さん──強い思いは、あまりない
4 マッチングセンターを取り巻く人々
5 地方は元気なシニアのサードプレイス
■事例17 医療をもっとカジュアルに語りたい──医カフェ・CoCo-Cam|青森県弘前市(秋田志保・平田朗子)
1 医学生が経営するカフェの誕生
2 筆者2人とCoCo-Camとの出会い
3 ゆるい場をつくる人(初代):白戸蓮さん──医学部では学べない社会的テーマを追求したい
5 ゆるい場をつくる人(2代目):佐々木慎一朗さん──遊びの天才ならではの実行力
6 仲間と共にビジョンを実践する
7 全国に医カフェができていく未来
■■終章 ゆるいからこそつながれる、続けられる(石山恒貴)
1 ゆるい場をつくる人々が歩む共通プロセス
2 ゆるい場は共振する
あとがき(石山恒貴)
女性やシニアの仕事場・減災/防災活動・医カフェ…
あるのは、人の数だけあるやりたいこと。
今「強制されない自発性=ゆるさ」が地域に、人に必要だ。出入り自由、フラットな関係、事務局が目立たない、楽しいから参加する、あるのは人の数だけあるやりたいこと。コワーキングスペースやまちの学び舎、コミュニティ農園、シェア本屋、女性やシニアの仕事場、減災・防災活動、医カフェなど、17のサードプレイスの物語
【目次】
■■序 ゆるい場としてのサードプレイス(石山恒貴)
1 ゆるさとは何か、なぜゆるい場が生まれるのか
2 ゆるい場の特徴と条件
3 ゆるい場をつくる人々
4 本書の4テーマ
■■1章 行きたい時に行ける場所
■事例1 「まちの非武装地帯」としてのコワーキングスペース──チガラボ|神奈川県茅ヶ崎市(石山恒貴)
1 まちの非武装地帯
2 理想のサードプレイスが存在した
3 ゆるい場をつくる人:清水謙さん──新しいことに1人で挑戦し続ける
4 チガラボという実験の始まり
5 交流×学習×実践のコミュニティ
6 まち自体が実験場になればいい
■事例2 まちの学校、コラーニングスペース──HLS弘前|青森県弘前市(石山恒貴)
1 まちの中でこそ実現する教育
2 ゆるい場をつくる人:辻正太さん──「ルイーダの酒場」(冒険する仲間を探す場所)をつくりたい
3 体育教師を目指した学生時代
4 中高一貫校の教師に
5 弘前で「ルイーダの酒場」を実現する
5 HLSの始動と成長
7 学校教育に戻る
■事例3 全員で運営するコモンズ農園──EdiblePark茅ヶ崎|神奈川県茅ヶ崎市(平田朗子)
1 会員制コミュニティ農園というチャレンジ
2 ゆるい場をつくる人:石井光さん──気さくな近所のお兄ちゃん
3 地主の13代目として辻堂で育つ
4 「巻き込まれ事故」のような流れで代表に
5 時間をかけて共存できるようになればいい
■事例4 みんなでみんなに大丈夫力をつける──サステナブルライフ研究会@湘南|神奈川県藤沢市(秋田志保)
1 有志のご近所メンバーでゆるく知識をシェアする会
2 住む人一人ひとりの安心感、大丈夫という感覚
3 ゆるい場をつくる人:齋藤佳太郎さん──生活用品の手作り実験から生まれたつながり
4 決めすぎない運営、選びすぎない人選
5 「軒先の未活用フルーツ」で湘南地域をつなげたい
■■2章 自分が行きたいと思える場所づくり
■事例5 十人十色、オトナたちのまちの学び舎──こすぎの大学|神奈川県川崎市(本多陽子・森隆広)
1 武蔵小杉に生まれた学び舎
2 ゆるい場をつくる人:岡本克彦さん──堅苦しくない伸び伸びとした居心地の良さ
3 会社以外の誰とも交流しない日常に気づいて
4 月1回、地域の懇親の場に新旧住民が集う
5 メンバーの思いはみんなバラバラ
6 住民の「やりたい」を後押しする、地域のハブ
■事例6 都心のコミュニティ菜園──そらとだいちの図書館|東京都新宿区(渡辺萌絵)
1 図書館の空地を活用したコミュニティ菜園
2 ゆるい場をつくる人:渡辺萌絵さん──場所も、資金も、人脈も、スキルも無い
3 自分にできる小さなことから──町内会長へ宛てた手紙とイラスト
4 空地を使った菜園イベント、多世代をつなぐ家族食堂、そして充電期間へ
5 ずっと気になっていた図書館の空地活用計画
6 試行錯誤しながら走り続ける
■事例7 イベント未満・カウンセリング未満の話せるシェア本屋──とまり木|神奈川県茅ヶ崎市(片岡亜紀子・谷口ちさ・平田朗子)
1 街に「リアルに話せる場所」を
2 とまり木に惹かれる理由
3 ゆるい場をつくる人:大西裕太さん──社会復帰から始まった場づくりの構想
4 みんなでつくるとまり木
5 訪問者が思い思いに過ごせる場所
■■3章 女性もシニアも心地よく働けるコミュニティ
■事例8 誰もが心地良く暮らし、働ける場をつくる──非営利型株式会社Polaris|東京都調布市(秋田志保・片岡亜紀子)
1 非営利型株式会社とは
2 ゆるい場をつくる人:市川望美さん──言葉と理念の人
3 誰もが自分で自分の働き方を選べるように
4 成長と拡大を経て感じた変化
5 生き方の選択肢を増やす
■事例9 シニアと仕事と地域をつなげる──NPO法人セカンドワーク協会|神奈川県茅ヶ崎市(小山田理佐・宮下容子)
1 シニアも現役世代も、共にセカンドワークを手に入れる
2 なぜNPO法人なのか──社会貢献活動への覚悟
3 ゆるい場をつくる人:四條邦夫さん──長年の会社員生活、起業、そしてNPO法人設立
4 試行錯誤した経験がつながっていく
5 仲間が増え、組織基盤を整えて活動の拡大を目指す
■事例10 「企業研修」をきっかけに会社員が地域にゆるく関わっていく──株式会社machimori|静岡県熱海市(佐々木梨華)
1 まちづくり会社が行う企業研修事業
2 ゆるい場をつくる人:佐々木梨華さん──machimoriの企業研修事業を立ち上げるまで
3 売るプログラムがない、顧客もいない、体制もない
4 machimoriの企業研修事業部のこれから
■■4章 楽しいから楽しい、地域活動
■事例11 富士山が微笑む若者のまちづくり── 一般社団法人F-design|静岡県富士市(石山恒貴)
1 若い世代が富士市を盛り上げる
2 個性が異なる3人の若者
3 ゆるい場をつくる人:大道和哉さん──F-designを立ち上げるまで
4 ゆるい場をつくる人:川上大樹さん──F-designに出会うまで
5 ゆるい場をつくる人:井出幸大さん──F-designに出会うまで
6 路線変更と信頼関係
7 社交交流型サードプレイスから、目的交流型サードプレイスへ
■事例12 人と農を結ぶ暮らしの創造──NPO法人湘南スタイル|神奈川県茅ヶ崎市(小山田理佐・近藤英明・佐藤雄一郎)
1 農業支援からはじまった湘南の老舗NPO法人
2 ゆるい場をつくる人:渡部健さん──農と食を通じて地域を盛り上げたい
3 やりたい人に任せる、緩いつながりの運営
5 街の人事部──住民が共に成長し支え合う
■事例13 楽しく備える新しい減災・防災のかたち──溝の口減災ガールズ|神奈川県川崎市(本多陽子)
1 減災・防災を「自分ごと」に
2 ゆるい場をつくる人:山本詩野さん──被災地へ支援に行ったつもりが、逆に刺激を受けて帰ってくる
3 近隣連携の副産物──「溝の口減災ガールズ」の誕生
5 マジメだけど軽やかに
6 できる時に、できるひとが、できることを
7 いざという時に手がつなげる安心感
■事例14 多様な関係人口とのつながりがまちを変える──ARUYO ODAWARA|神奈川県小田原市(大川朝子)
1 多様な関係人口が行き交う都市のコミュニティ
2 ゆるい場をつくる人:コアゼユウスケさん──人生は学校ではなく、すべてタワーレコードから教わった
4 住民・移住者・リモートワーカーが集まる場で好循環が生まれる
5 楽しく生きる大人を増やす
■事例15 面白そう、楽しそうでつながる里山のコミュニティ─ ──バー洋子・焚き火編集室|福岡県宗像市(北川佳寿美)
1 多彩な顔をもつデザイナー
2 ゆるい場をつくる人:谷口竜平さん──田舎での暮らしと、都会への屈折した憧れ
3 かっこいい大人とかっこいい仕事
4 「田舎はいい」が初めて腑に落ちた瞬間
5 一万坪の里山でゆるく地域とつながり続ける
■事例16 定年後に地域とゆるくつながる──ながはま森林マッチングセンター・星の馬WORKS・もりのもり|滋賀県長浜市(八代茂裕)
1 山を活かす、山を守る、山に暮らす
2 マッチングセンターとのゆるく心地よい関係
3 ゆるい場をつくる人:橋本勘さん──強い思いは、あまりない
4 マッチングセンターを取り巻く人々
5 地方は元気なシニアのサードプレイス
■事例17 医療をもっとカジュアルに語りたい──医カフェ・CoCo-Cam|青森県弘前市(秋田志保・平田朗子)
1 医学生が経営するカフェの誕生
2 筆者2人とCoCo-Camとの出会い
3 ゆるい場をつくる人(初代):白戸蓮さん──医学部では学べない社会的テーマを追求したい
5 ゆるい場をつくる人(2代目):佐々木慎一朗さん──遊びの天才ならではの実行力
6 仲間と共にビジョンを実践する
7 全国に医カフェができていく未来
■■終章 ゆるいからこそつながれる、続けられる(石山恒貴)
1 ゆるい場をつくる人々が歩む共通プロセス
2 ゆるい場は共振する
あとがき(石山恒貴)
- 本の長さ320ページ
- 言語日本語
- 出版社学芸出版社
- 発売日2024/9/15
- 寸法18.8 x 12.7 x 2 cm
- ISBN-104761529075
- ISBN-13978-4761529079
よく一緒に購入されている商品
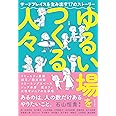
対象商品: ゆるい場をつくる人々: サードプレイスを生み出す17のストーリー
¥2,640¥2,640
最短で4月24日 木曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥1,100¥1,100
最短で4月24日 木曜日のお届け予定です
残り12点(入荷予定あり)
¥2,640¥2,640
最短で4月24日 木曜日のお届け予定です
在庫あり。
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
3をすべてカートに追加する
一緒に購入する商品を選択してください。
似た商品をお近くから配送可能
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
出版社より
●出入り自由でフラットで楽しいから参加する

今「強制されない自発性=ゆるさ」が地域に、人に必要だ。出入り自由、フラットな関係、事務局が目立たない、楽しいから参加する、あるのは人の数だけあるやりたいこと。コワーキングスペースやまちの学び舎、コミュニティ農園、シェア本屋、女性やシニアの仕事場、減災・防災活動、医カフェなど、17のサードプレイスの物語
●紙面Sample




商品の説明
著者について
■編著者
石山 恒貴(いしやま のぶたか)
法政大学大学院教授。一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。越境的学習、キャリア形成、人的資源管理、タレントマネジメント等が研究領域。日本労務学会副会長、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、人事実践科学会議共同代表、一般社団法人シニアセカンドキャリア推進協会顧問、NPO法人二枚目の名刺共同研究パートナー、フリーランス協会アドバイザリーボード、専門社会調査士等。主な著書に『地域とゆるくつながろう――サードプレイスと関係人口の時代』『カゴメの人事改革: 戦略人事とサステナブル人事による人的資本経営』『越境学習入門ー組織を強くする冒険人材の育て方ー』『日本企業のタレントマネジメント』など。
■著者
秋田 志保(あきた しほ)
料理家/法政大学大学院政策創造研究科研究生、修士(政策学)
大川 朝子(おおかわ ともこ)
出版社勤務/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
小山田 理佐(おやまだ りさ)
地域ICT化支援講師/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
片岡 亜紀子(かたおか あきこ)
早稲⽥大学グローバルエデュケーションセンター講師/法政大学大学院兼任講師/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)
北川 佳寿美(きたがわ かずみ)
キャリアコンサルタント・精神保健福祉士/法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修士課程修了、修士(キャリアデザイン学)
近藤 英明(こんどう ひであき)
不動産会社勤務/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程在籍、修士(政策学)
佐々木 梨華(ささき りか)
社会事業コーディネーター(一般社団法人RCF/株式会社machimori)/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
佐藤 雄一郎(さとう ゆういちろう)
教育機関勤務/消費者関連事業者団体研究所長/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)
谷口 ちさ(たにぐち ちさ)
高知大学学び創造センターキャリア開発ユニット特任助教/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程在籍、修士(政策学)
平田 朗子(ひらた さえこ)
人材サービス会社PMO/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
本多 陽子(ほんだ ようこ)
フリーランスPR/法政大学大学院政策創造研究科研究生、修士(政策学)
宮下 容子(みやした ようこ)
法政大学大学院政策創造研究科修士課程在籍
森 隆広(もり たかひろ)
企業人事/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
八代 茂裕(やしろ しげひろ)
短期大学職員/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
渡辺 萌絵(わたなべ もえ)
キャリアコンサルタント/そらとだいちの図書館コミュニティリーダー/法政大学大学院政策創造研究科修士課程在籍
石山 恒貴(いしやま のぶたか)
法政大学大学院教授。一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。越境的学習、キャリア形成、人的資源管理、タレントマネジメント等が研究領域。日本労務学会副会長、人材育成学会常任理事、産業・組織心理学会理事、人事実践科学会議共同代表、一般社団法人シニアセカンドキャリア推進協会顧問、NPO法人二枚目の名刺共同研究パートナー、フリーランス協会アドバイザリーボード、専門社会調査士等。主な著書に『地域とゆるくつながろう――サードプレイスと関係人口の時代』『カゴメの人事改革: 戦略人事とサステナブル人事による人的資本経営』『越境学習入門ー組織を強くする冒険人材の育て方ー』『日本企業のタレントマネジメント』など。
■著者
秋田 志保(あきた しほ)
料理家/法政大学大学院政策創造研究科研究生、修士(政策学)
大川 朝子(おおかわ ともこ)
出版社勤務/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
小山田 理佐(おやまだ りさ)
地域ICT化支援講師/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
片岡 亜紀子(かたおか あきこ)
早稲⽥大学グローバルエデュケーションセンター講師/法政大学大学院兼任講師/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)
北川 佳寿美(きたがわ かずみ)
キャリアコンサルタント・精神保健福祉士/法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修士課程修了、修士(キャリアデザイン学)
近藤 英明(こんどう ひであき)
不動産会社勤務/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程在籍、修士(政策学)
佐々木 梨華(ささき りか)
社会事業コーディネーター(一般社団法人RCF/株式会社machimori)/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
佐藤 雄一郎(さとう ゆういちろう)
教育機関勤務/消費者関連事業者団体研究所長/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)
谷口 ちさ(たにぐち ちさ)
高知大学学び創造センターキャリア開発ユニット特任助教/法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程在籍、修士(政策学)
平田 朗子(ひらた さえこ)
人材サービス会社PMO/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
本多 陽子(ほんだ ようこ)
フリーランスPR/法政大学大学院政策創造研究科研究生、修士(政策学)
宮下 容子(みやした ようこ)
法政大学大学院政策創造研究科修士課程在籍
森 隆広(もり たかひろ)
企業人事/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
八代 茂裕(やしろ しげひろ)
短期大学職員/法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了、修士(政策学)
渡辺 萌絵(わたなべ もえ)
キャリアコンサルタント/そらとだいちの図書館コミュニティリーダー/法政大学大学院政策創造研究科修士課程在籍
登録情報
- 出版社 : 学芸出版社 (2024/9/15)
- 発売日 : 2024/9/15
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 320ページ
- ISBN-10 : 4761529075
- ISBN-13 : 978-4761529079
- 寸法 : 18.8 x 12.7 x 2 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 128,264位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 458位福祉の社会保障
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

高知大学 学び創造センター キャリア開発ユニット 特任助教
関西大学社会学部卒業、法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了(政策学修士)、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程在籍。日本IBM研修サービス(のちに日本IBM人事部門)、ファミリーマート、大地を守る会(現・オイシックス・ラ・大地)、フリーランスを経て、現職。
研究領域:メンタリング、デベロップメンタル・ネットワーク、越境学習、キャリア開発 等
共著:『地域とゆるくつながろう ~サードプレイスと関係人口の時代~』(石山恒貴 編著)、『ゆるい場をつくる人々 ~サードプレイスを生み出す17のストーリー』(石山恒貴 編著)。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.3つ
5つのうち4.3つ
9グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ60%25%0%15%0%60%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ60%25%0%15%0%25%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ60%25%0%15%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ60%25%0%15%0%15%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ60%25%0%15%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年11月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入成果のある様々な組織の取材をしているのかと思いきや、ある組織を起点に紹介、取材申し込みしているのが、大半です。そのために、成果がどうでてるのか、怪しいところが随所で感じられます。設立者の人生観(想い)に注目してばかりで、データはまずないです。どの事例も、綺麗事で具体性がみえない印象です。学生さん(といっても院生なので年齢層は様々ですが)なので、文章力、構成力が読みにくい箇所があります。誰が誰のことを書いているのか、写真に複数人写ってるのであれば誰が誰なのか、内輪の共同論文ではないので、読みものとしては、しっかりしてほしいところです。
- 2024年9月25日に日本でレビュー済み日本の企業組織が共同体的な側面を持ち、それがいま、あり方を問われている。そもそも共同体的な側面、つまり会社が共同体のような性格を帯びるのは、社外にコミュニティが存在しなかったことが一因だと考えられる。
ただ欧米と違ってわが国では純然たるコミュニティ、本書で言うところの「社交交流型」のようなコミュニティは広がりにくい。その点、本書でたくさん紹介されている「目的交流型」の広がりに期待が持てる。小規模なコミュニティがあちこちに誕生し、人々が会社だけでなくコミュニティにも関わるのが標準的なスタイルになれば、日本社会も成熟していくのではないか。