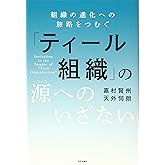Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現 単行本 – 2018/1/24
購入オプションとあわせ買い
【大反響、10万部突破!! 】
これから私たちは、
どんな組織・働き方・社会を選ぶのか?
世界17カ国・60万部突破!
歴史的スケールで解き明かす
組織の進化と人間社会の未来。
数万人規模のグローバル企業から先進的な医療・介護組織まで、
膨大な事例調査から導き出した新時代の組織論。
続々受賞!
「ビジネス書大賞2019」経営者賞
「読者が選ぶビジネス書グランプリ 2019」マネジメント部門
「ITエンジニアに読んでほしい! 技術書・ビジネス書 大賞 2019」ベスト10 「HRアワード 2018」優秀賞
■各界から共感の声!
読んでいるとアイデアがどんどんわいてくる。」
――岡田武史(株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役会長)
10年、20年先の組織のあり方を示す決定版こそが「ティール」
この変化が、様々な業界で既に起きつつあることに、興奮を隠せない!
――入山章栄(早稲田大学ビジネススクール准教授、『世界の経営学者はいま何を考えているのか』著者)
わくわくする社会が、世界が、未来が待っている。
――島田由香(ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス)
この本によって、「働きづらさ」を抱えている人たちも働きやすくなる、そんなチャンスが一気に増えそうだ。
――成澤俊輔(株式会社YOUTURN)
この島にいるすべての人が、やりがいあふれる仕事や暮らしに没頭できる。そんなふうに変われたら、それを「ティール社会」と言うのかもしれない。
――阿部裕志(風と土と)
本書の価値は、「個人の目的の追求と、組織がもつ潜在力の活用をどうすれば両立できるか」という問いに真剣に向き合った点にある。
――永山晋(法政大学)
久しぶりに画期的な組織論の本に出会った。
――堀内勉(多摩大学大学院特任教授、書評サイトHONZレビュアー)
これは間違いなく、今後20年は読みつがれる組織論の古典になる。
――岩佐文夫(元DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集長)
「なぜ仕事で疲弊するのか」 「組織のどこがおかしいのか」?と思ったら
原因を究明するのに最高の教科書。
――吉沢康弘(インクルージョン・ジャパン取締役)
「高い次元の組織」とは何か、という問いに答える刺激的な一冊。
――ロバート・キーガン(ハーバード大学教育大学院教授、『なぜ人と組織は変われないのか』著者)
ポスト資本主義時代における新しい組織モデルのバイブルとして、
21世紀の歴史に刻まれる本になるでしょう。
――佐宗邦威(biotope代表/戦略デザイナー、『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』著者)
◆「ティール」とは 著者は人類の歴史における組織の進化を色の波長で表現しました。
最新の「進化型(ティール)組織」は、世界各地で現れつつある
まったく新しいマネジメント手法を採用する組織のことを指します。
[組織モデルの発達段階]
衝動型(レッド)……組織生活の最初の形態、数百人から数万人の規模へ。力、恐怖による支配。
自他の区分、単純な因果関係の理解により分業が成立
例)マフィア、ギャングなど
順応型(アンバー)……部族社会から農業、国家、文明、官僚制の時代へ。
時間の流れによる因果関係を理解し、計画が可能に。
規則、規律、規範による階層構造の誕生
例)教会、軍隊、官僚組織など
達成型(オレンジ)……科学技術の発展と、イノベーション、起業家精神の時代へ。
「命令と統制」から「予測と統制」へ。実力主義の誕生。
効率的で複雑な階層組織
例)多国籍企業など
多元型(グリーン)……多様性と平等と文化を重視するコミュニティ型組織の時代へ。
ボトムアップの意思決定、多数のステークホルダー。
例)コミューン、非営利組織、サウスウエスト航空など
進化型(ティール)……変化の激しい時代における生命体型組織の時代へ。
自主経営(セルフ・マネジメント)、全体性(ホールネス)、存在目的を重視する独自の慣行をもつ。
◆本書で取り上げられる企業事例(本文より抜粋)
AES……エネルギー/グローバル/従業員4万人/営利企業
AESは、ロジャー・サントとデニス・バーキによって1982年に米国で設立され、
その後短期間で世界トップクラスの電力会社の地位に上り詰めた。
世界中に12の発電所を構え、従業員数は4万人。
BOS/オリジン……ITコンサルティング/グローバル/従業員1万人(1996年時点)/営利企業
BOS/オリジンはエッカルト・ウインツェンによって一九七三年にオランダで設立された。
1996年にウインツェンが事業をフィリップスに売却して同社を去ったときには、
20カ国に1万人の従業員を抱えていた。
ビュートゾルフ……ヘルスケア/オランダ/従業員七万人/非営利組織
ビュートゾルフはヨス・デ・ブロックと一組の看護師チームによって、2006年に設立された非営利組織。
現在はオランダ最大の地域看護師の組織として、高齢者や病人の在宅ケアサービスを提供している。
ESBZ……学校(第7〜12学年)/ドイツ/生徒数1500名と職員、保護者/非営利組織
ベルリンセンター福音学校(ESBZ)は、同校のディレクターであるマーグレット・ラスフェルトが主導して、
2007年にベルリンで設立された公立学校。
その革新的なカリキュラムと組織モデルが国際的な注目を集めている。
FAVI……金属メーカー/フランス/従業員500名/営利企業
FAVIは、もともとは家族経営の金属部品メーカーとして1957年にフランス北部で設立された。
1983年に、ジャン・フランソワ・ゾブリストがCEOに就任し、抜本的な組織の変革に取り組みはじめた。
主力製品は自動車産業向けのギアボックス・フォーク。
ハイリゲンフェルト……メンタルヘルス病院/ドイツ/従業員600名/営利企業
ハイリゲンフェルトは現在、リハビリテーション・センターと4つのメンタルヘルス病院をドイツ中央地域で運営している。
同社はヨアヒム・ガルスカ、フリッツ・ランの両博士により1990年に設立された。
ガルスカはこの病院を立ち上げる前、従来型のメンタルヘルス病院で自分のビジョンを包括的
アプローチによる精神疾患の治療に適用しようとして失敗したという経験をしている。
ホラクラシー……組織運営モデル
ホラクラシーは組織運営モデルのことで、もともとはフィラデルフィアのスタートアップ企業ターナリー・ソフトウェアの
ブライアン・ロバートソンがチームメンバーと共に開発した。ターナリーの経営を次のリーダーに引き継いだあと、
ロバートソンは、研修、コンサルティング、リサーチ企業のホラクラシーワンを共同設立した。
同社はこの新モデルの普及を事業としており、規模の大小を問わず世界中の営利、非営利組織で採用されるようになった。
モーニング・スター……食品加工/米国/従業員400~2400名/営利企業
モーニング・スターはクリス・ルーファーによって一九七〇年に設立されたトマト専門の生産・運送業者で、
今日、アメリカ合衆国におけるトマトの加工および運送分野で圧倒的なシェアを確保している。
パタゴニア……アパレル/米国/従業員1350名/営利企業
イヴォン・シュイナードという、おそらく史上最もビジネスとは縁遠いと思われる男が、
のちに「パタゴニア」と呼ばれる企業を設立してピトン(登山用の鉄製のくさび)の生産を始めたのが1957年。
カリフォルニアを拠点とするこの会社は、世界的なアウトドア用品メーカーに成長し、環境問題の改善
に本格的に取り組んでいる。
RHD……人事/米国/従業員4000名/非営利組織
リソーシズ・フォー・ヒューマン・ディベロップメント(RHD)は、フィラデルフィアを拠点にアメリカ合衆国の一四州で事業展開をしている非営利組織。
精神疾患、各種依存症からの回復、ホームレスといった分野でさまざまな形態の住居やシェルター、各種プログラムを提供して
支援を求める人々にサービスを提供している。ロバート・フィッシュマンによって一九七〇年に設立された。
サウンズ・トゥルー……メディア/米国/従業員90名と犬20匹/営利企業
サウンズ・トゥルーは、スピリチュアル・マスター(霊的な能力がある人たち)の録音、書籍、オンライン研修プログラム、
音楽などを通じて霊的な知恵を広める事業を行っている。タミ・サイモンによって一九八五年に設立された。
サン・ハイドローリックス……油圧部品/グローバル/従業員900名/営利企業
サン・ハイドローリックスは二人のエンジニアによって1970年に設立され、
油圧カートリッジ・バルブとマニホールドの設計および製造を手がけている。
現在はフロリダ(本社所在地)、カンザス、イギリス、ドイツ、韓国に工場を構える上場企業である。
- 本の長さ592ページ
- 言語日本語
- 出版社英治出版
- 発売日2018/1/24
- 寸法13.1 x 3.6 x 21.1 cm
- ISBN-104862762263
- ISBN-13978-4862762269
よく一緒に購入されている商品
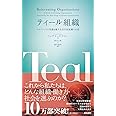
似た商品をお近くから配送可能
出版社より

これから私たちは、どんな組織・働き方・社会を選ぶのか?
世界17カ国・60万部突破! 歴史的スケールで解き明かす 組織の進化と人間社会の未来。
数万人規模のグローバル企業から先進的な医療・介護組織まで、膨大な事例調査から導き出した新時代の組織論。
組織の進化パラダイム

「ティール」とは・・・著者は人類の歴史における組織の進化を色の波長で表現しました。最新の「進化型(ティール)組織」は、世界各地で現れつつあるまったく新しいマネジメント手法を採用する組織のことを指します。

著者:フレデリック・ラルー Frederic Laloux
マッキンゼーで10年以上にわたり組織変革プロジェクトに携わったのち、エグゼクティブ・アドバイザー/コーチ/ファシリテーターとして独立。2年半にわたって新しい組織モデルについて世界中の組織の調査を行い、本書を執筆。17カ国語に翻訳され60万部を超えるベストセラーとなる。現在は家族との生活を最も大切にしながら、気候危機を止めるプロジェクトに注力している。

【関連コンテンツのご紹介】
英治出版では『ティール組織』をより深く理解し,活用していただくための様々な取り組みを行っています。
【読書会ガイドを無料公開!】
本書の出版以降、各地で多くの読書会が開かれています。 そこで、解説者の嘉村賢州さんのご協力を得て、主催者・ファシリテーターのための「読書会ガイド」を作成しました。 さまざまな状況を想定した場づくりのヒントをまとめていますので、お役立ていただければ幸いです。 また、多人数で同時に読書・対話を行う「Active Book Dialogue」を行われる方には、無料でゲラ(原稿の刷り出し)を提供いたします!本を断裁・分割することなく、読書会を開催していただけます。 関心ある方は「ティール組織 英治出版」で検索して弊社の書籍ページをご覧ください。
【オンラインメディアで関連情報を無料公開! 】
「英治出版オンライン」では英治出版の書籍をより楽しむコンテンツ、よりよい未来をつくるアイデア、読者を応援する企画を発信。ティール組織の第一人者による連載や識者へのインタビューなども掲載しています。
下記の連載以外にも、日本初のティール組織カンファレンスのレポートや、著者の講演動画など多彩なコンテンツをご用意。ひとりでも多くの方のヒントとなれば幸いです。ぜひ「英治出版オンライン」のウェブサイトを訪れてみてください。
【 ティール組織に関連する連載記事】

「『ティール組織』私はこう読んだ。| 英治出版オンライン」
『ティール組織』を各界のリーダーや研究者はどう読んだか。元サッカー日本代表監督、東京大学の社会学者、地方活性を担う社会イノベーターなど多様な視点から組織や社会の進化を考える。

「Teal Impact | 英治出版オンライン」
なぜ「ティール組織」がここまで注目されるのか? これまでどのような取り組みがあり、これからどんな動きが生まれるのか? 多角的な視点から、「日本の組織と社会のこれから」を探求する。

「Next Stage Organizations | 英治出版オンライン」
ティール組織研究の第一人者である嘉村賢州さん・吉原史郎さんによるレポート。業界や国境を越えて次世代型組織(Next Stage Organizations)を探究する旅に出る。
商品の説明
出版社からのコメント
【読書会ガイドを無料公開!】
本書の出版以降、各地で多くの読書会が開かれています。
そこで、解説者の嘉村賢州さんのご協力を得て、
主催者・ファシリテーターのための「読書会ガイド」を作成しました。
さまざまな状況を想定した場づくりのヒントをまとめていますので、お役立ていただければ幸いです。
また、多人数で同時に読書・対話を行う「Active Book Dialogue」を行われる方には、
無料でゲラ(原稿の刷り出し)を提供いたします!
本を断裁・分割することなく、読書会を開催していただけます。
関心ある方は「ティール組織 英治出版」で検索して弊社の書籍ページをご覧ください。
【オンラインメディアで関連情報を無料公開! 】
英治出版オンラインで、ティール組織の第一人者による連載や識者へのインタビューなどを掲載しています。
以下のキーワードで検索してチェックしてみてください。
「Next Stage Organizations|英治出版オンライン」
ティール組織研究の第一人者である嘉村賢州さん・吉原史郎さんによる探求レポート
「Teal Impact|英治出版オンライン」
なぜ「ティール組織」がここまで注目されているのか? これまでどのような取り組みがあったのか? そして、これからどんな動きが生まれるのか? 多角的な視点から、「日本の組織と社会のこれから」を探求する。
「『ティール組織』私はこう読んだ。|英治出版オンライン」
『ティール組織』を各界のリーダーや研究者はどう読んだか。多様な視点から組織や社会の進化を考える。
著者について
フレデリック・ラルー Frederic Laloux
マッキンゼーで10年以上にわたり組織変革プロジェクトに携わったのち、エグゼクティブ・アドバイザー/コーチ/ファシリテーターとして独立。2年半にわたって新しい組織モデルについて世界中の組織の調査を行い、本書を執筆。12カ国語に翻訳され20万部を超えるベストセラーとなる。現在は家族との生活を最も大切にしながら、コーチや講演活動などを行い本書のメッセージを伝えている。
[訳者]
鈴木立哉 Tatsuya Suzuki
実務翻訳者。一橋大学社会学部卒業。コロンビア大学ビジネススクール修了(MBA)。野村証券勤務などを経て2002年から現職。専門はマクロ経済や金融分野の英文レポートと契約書等の翻訳。著書に『金融英語の基礎と応用 すぐに役立つ表現・文例1300』(講談社)、訳書に『世界でいちばん大切にしたい会社』(翔泳社)、『Q思考』(ダイヤモンド社)など。
[解説]
嘉村賢州 Kenshu Kamura
場づくりの専門集団NPO法人場とつながりラボhome's vi代表理事。コクリ! プロジェクト ディレクター(研究・実証実験)。京都市未来まちづくり100人委員会 元運営事務局長。集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。研究領域は紛争解決の技術、心理学、脳科学、先住民の教えなど多岐にわたり、国内外問わず研究を続けている。実践現場は、まちづくりや教育などの非営利分野や、営利組織における組織開発やイノベーション支援など、分野を問わず展開し、ファシリテーターとして年に100回以上のワークショップを行っている。2015年に1年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORG LAB)」を設立、現在に至る。
登録情報
- 出版社 : 英治出版 (2018/1/24)
- 発売日 : 2018/1/24
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 592ページ
- ISBN-10 : 4862762263
- ISBN-13 : 978-4862762269
- 寸法 : 13.1 x 3.6 x 21.1 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 3,963位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 50位マネジメント・人材管理
- - 526位投資・金融・会社経営 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について

マッキンゼーで10年以上にわたり組織変革プロジェクトに携わったのち、エグゼクティブ・アドバイザー/コーチ/ファシリテーターとして独立。2年半にわたって新しい組織モデルについて世界中の組織の調査を行い、本書を執筆。12カ国語に翻訳され20万部を超えるベストセラーとなる。現在は家族との生活を最も大切にしながら、コーチや講演活動などを行い本書のメッセージを伝えている。
カスタマーレビュー
お客様のご意見
お客様はこの書籍について、以下のように評価しています: 内容については、大変勉強になったと感じています。素晴らしい示唆と事例が提供され、多くの読者に勇気を与えたという声があります。また、組織形態についても、新しい組織形態としてのティール組織の特徴をしっかりと理解できると好評です。 組織の在り方についても、自組織に活かせる部分が多く、魂が震える組織論だと評価されています。 自主性を促し、自己決定権や情報の公開、情報公開、自己決定権といった特徴を指摘する声もあります。 知性の面では、暗黙知が形式知化されていることが評価されており、一人ひとりの持つ能力が真に発揮される組織の在り方が示されているとの声もあります。
お客様の投稿に基づきAIで生成されたものです。カスタマーレビューは、お客様自身による感想や意見であり、Amazon.co.jpの見解を示すものではありません。
お客様はこの書籍について、大変勉強になったと評価しています。マネジメントに携わる全ての人にとって読む価値がある良書だと感じています。また、概念的な内容で論理的に紡がれており、行動心理学を学べる良書だと好評です。500ページというボリュームにもかかわらず、多くの読者が新たな気づきを得ることができると述べています。
"自己啓発にはおすすめの1冊です。" もっと読む
"今、自分が所属している組織と照らし合わせて読むと非常に面白いです。前半に比べて後半は読みづらいところもありましたが、ビジネスに限らずあらゆる組織に所属し、そのマネジメントに疑問を持たれている方は是非とも一読する価値があると思いました。" もっと読む
"これはとても良い本。新しい時代の組織について書かれた一冊。580ページもあるが、理論整然としているし、具体例も多いので極めて読みやすい。著者の言う新しい組織形態は進化型evolutionary組織と呼ばれる。その組織には指示関係を表す組織図もないし、全社戦略も、全社の予算もない。..." もっと読む
"...ボリュームが相当ある本で、内容の繰り返しと共に飽きは来る。が、私の所属する組織と比較しつつ、各個人はどうやったら自分らしく振る舞えるだろうかなどと考えながら、ゆっくり読み進めた。..." もっと読む
お客様はこの書籍について、新しい組織形態としてのティール組織の特性を理解できたと評価しています。組織論の原書として挙げられており、自組織に活かせる部分が多くあるようです。また、体系的にまとめてあり、分かりやすい内容だと感じています。特に、進化型組織の作り方や、組織を階層化せず、経営状況や成果をオープンにした上で権限を与えるという意見もあります。
"...最終章は進化型組織の作り方。進化型組織は一度できてしまえば、もう安泰なのではない。CEO(進化型組織は階層がなく最高責任者という概念はふさわしくないが、いわゆるCEO)や取締役会の理解がなければ、進化型組織もすぐに従来型に戻ってしまう(p.420-427)。..." もっと読む
"...正直、話題になっていた当時はただの組織論の本かと思ってましたが、内容を読んで驚愕しました。 これは大げさに言えば人類の進化、人と集団の歴史、文化人類学を描いた本です。..." もっと読む
"たしかに素晴らしい新組織形態を紹介しているが、決して万能な組織形態とは言っていない点に注意が必要。実際にティール組織を目指さなくても、知るだけでも価値があると思うので、星4つ" もっと読む
"体系的にまとめてあり、分かり易い。" もっと読む
お客様はこの書籍の読みやすさを高く評価しています。読みやすく、訳も素晴らしいと感じています。参考書的な感じで細かい文章が並べられている点も好評です。ただし、読書が苦手な方には少々きついと感じる方もいますが、全体的には参考になる内容だと感じているようです。
"久しぶりに良い本に出会いました。 まず、伝えようとする作者の熱意が伝わってくること(訳も素晴らしいのでしょう) 広い世界観(会社、組織、個人、社会、歴史的大観、広がりと深み)との整合性..." もっと読む
"読み易かつたです。訳者は、優秀な方だと感じました。関連文書が巻末にあります。" もっと読む
"...本書はその素晴らしい示唆と事例を教えてくれ、大変勇気をもらいました。 組織の範疇を遥かに超える新しい人類進化論です。 翻訳も大変素晴らしいです。" もっと読む
"久々の大作読破でした(汗)とはいえ、割と概念的な内容で、話題の繰り返しの部分も多いため、600ページとは言え、意外と読みやすい一冊でした。ソフトカバーで、文字は小さめ。余白もあるので、メモも書き込めます。 内容は、他のレビューの方々、皆さまが詳細に記載されているので省きます。..." もっと読む
お客様はこの本について、自主性を促し、自分らしさを失わずに働き、成果を上げることを推奨しています。権限の委譲とフラットな形態、情報の完全公開、自己決定権などの特徴が挙げられています。また、自主経営という特徴も驚きです。
"...進化型(ティール)組織とは、自主経営、全体性、存在目的の3つの特徴を備えたものです。..." もっと読む
"ティール組織を是非実践したいと思う! 権限の委譲とフラットな形態、情報の完全公開と自己決定権。沢山の示唆を頂いた!さらに読み込みたい!" もっと読む
"自主経営という特徴には驚き..." もっと読む
"自主性を促し、自分らしさを失わずに働き、かつ成果もあげる、そんな次世代組織について紹介する本..." もっと読む
お客様はこの書籍について、集団的知性や集団対話によって階層を不要にする「自主経営」の理念を高く評価しています。暗黙知が形式知化され、一人ひとりの持つ能力が真に発揮される組織の在り方が示されていると感じています。また、成熟社会の先に見える組織の在り方も示されており、個人と組織・社会との境界をなくし、一人ひとりの持つ能力が真に発揮できる組織の在り方が教えられています。
"成熟社会の先に見える組織の在り方が示されている良書です。一人ひとりの持つ能力が真に活かされ、発揮させられる組織の在り方が教えられています。一足飛びには今の組織を変更することはできませんが、近未来に目指すべき組織の在り方を学ぶ上で、大変参考になります。" もっと読む
"...著者が提唱する「ティール組織」では、信頼と対話及び集団的知性によって階層を不要にする「自主経営」、個人と組織・社会との間の境界を排除することでより自分らしく働くための「全体性」、組織が何のために存在するのかを常に問い続ける「存在目的」により、組織は一つの「生命体」として様々なトレードオフを克服し、..." もっと読む
"暗黙知が形式知化された!最高の本。..." もっと読む
イメージ付きのレビュー
ティール組織を目指さなくても知る価値有り
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年7月22日に日本でレビュー済みAmazonで購入自己啓発にはおすすめの1冊です。
- 2021年2月20日に日本でレビュー済みAmazonで購入今、自分が所属している組織と照らし合わせて読むと非常に面白いです。前半に比べて後半は読みづらいところもありましたが、ビジネスに限らずあらゆる組織に所属し、そのマネジメントに疑問を持たれている方は是非とも一読する価値があると思いました。
- 2018年2月8日に日本でレビュー済みAmazonで購入これはとても良い本。新しい時代の組織について書かれた一冊。580ページもあるが、理論整然としているし、具体例も多いので極めて読みやすい。著者の言う新しい組織形態は進化型evolutionary組織と呼ばれる。その組織には指示関係を表す組織図もないし、全社戦略も、全社の予算もない。現場の小さな人数からなるチームが権限を持ち、現場でおよそすべての意思決定を行う。進化型組織の人々は利益を追わないし、自分らしく生き生きと働く。
こんな特性の組織を聞くと、特に営利組織として存在することは夢物語に見える。だが著者はこうした組織を実際に発見し、調査し、その特徴を描き出す。こうした新しい組織形態を模索しているパイオニア組織は、互いの存在を知らず、セクターや規模にかかわらず驚くほど似たような組織構造と慣行にたどり着いている(p.20f)。本書はそうした知らずのうちに共通した、進化型組織の特性をとても分かりやすく書く。すぐに様々な疑問に浮かぶーーやる気のない従業員・フリーライダーへの対処、予算配分、人事考査、報酬体系、採用、チーム間で意見が対立する際の調停、マネジメント、法務や財務などのバックオフィス機能、利益を求める株主への対処。こうした事柄に、進化的組織は対処する方法を持っている。具体例を挙げて明快に示される。頻出するのはオランダの高齢者訪問看護組織のビュートゾルフ、フランスの金属部品メーカーFAVI。他にはグローバルな電力会社AES、アメリカのトマト加工食品会社モーニング・スターなど。日本のネット企業オズビジョンも少し登場する。
著者の組織観は、人間の発達心理学的な発達段階が基礎になっている。単なる受動的な段階から、神秘的、衝動型、順応型、達成型、多元型と名付けられた段階を経て、進化型に至る。この分類と特徴づけはクリアで、ここだけでも価値は高い。ちなみに著者はこうした人間の意識の発達段階を、インテグラル理論に倣って色で表す。ただし色名の付け方は部分的に異なっている(p.28)。邦題にもなっているティール(原題は「組織の再発明」)とは、カモの一種。特にマガモの首の、深い緑から青に至る色を指す。ただ、この色名はさして意味がない。何か思い入れがあるような記述もあるが、なぜ各発達段階にその色名が付けられているのかは説明されない。「進化型」など、それぞれの段階を特徴づける名前がきちんとつけられているので、色名はまったく無視してよいだろう。「ティール組織」なんて名前でなく、きちんと「進化型組織」としてこの概念が広まってほしい。
ここでは発達段階とされているので、あたかもここには階層秩序があって、下位の段階は劣るように見える。本書は明確にそう扱っていないが、読み手は序列を見るだろう。それは間違いだろう。それぞれの環境に応じて、適切な発達段階、組織形態がある。特に新しい段階の組織が生まれるスピードは加速しており、現代は多くの段階の組織が隣り合わせに活動している(p.61f)。ここに序列を読み込むのは先入観に過ぎない。ちなみに参考文献を見るに、この発達心理学的なところは、組織学や経営理論に比べて古い。著者がメインに参考にしているのは例えばケン・ウィルバーなのだが、議論自体の古さは頭のどこかに置いておいたほうが良いだろう。
現代の社会では多くの組織は達成型である。そして多元型が達成型を克服するものとして見られている。達成型の発達段階では人間は自由に人生の目的を追求する。ここでは成功する(出世する、金持ちになる)ことが中心だ。達成型組織は現代のグローバル企業に体現される。イノベーション、説明責任、実力主義がそれを彩る。ただし達成型組織の問題はイノベーションの行き過ぎ。ニーズを無理やり作り出そうとし、成長のための成長を目指す。こうした組織は、医学的には癌そのものといえる(p.57f)。
著者は最後のほうでは、この発達段階の比喩を組織形態のみならず、社会全体にも拡張する。順応型なら封建制社会、達成型社会に至って産業革命が起こるなど。すると、進化型社会では自然との共生、利子なき金融システム、所有権から管理責任へ、といったところがキーワードになる(p.487-497)。
各組織の発達段階を決めるのはリーダーの発達段階だ。リーダーがどのパラダイムを通じて世界を見ているかが、組織を決める。どんな組織もリーダーの発達段階を超えて進化することはない(p.70-72)。ゆえ、組織のミドル層とかからの変革はほぼ無理。進化型組織になれるかは経営トップと組織オーナーの世界観で決まる(p.394-396, 445)。組織の発達段階に応じて、その中の人の振る舞いも作られていく(p.133)。軍隊的な組織にいれば、是非を考えず服従を主とする人間になる。このことは、四象限を用いてうまく語られる。それは個別的/集合的、内面的/外面的の軸からなる。個別的で外面的なもの、すなわち観察可能な個人(リーダー)の行動が起点となり、それが集合的・外面的なもの(組織のプロセス)と集合的・内面的なもの(組織文化)を作り、個別的・内面的なもの(個人の心の持ち方)を作っていく(p.380-382)。
進化型の発達段階とは、自分自身のエゴ、私利私欲を切り離した段階。ここでは独りよがりの思いや、他人の評価や外的基準によって人は動くのではない。全体と調和した、自ら正しいと信じる信念に基づいて行動する(p.74-76)。こうしたエゴの超越は、著者においては後ろにスピリチュアルなものが控えている。超越的な精神領域への解放と、自分が大きな完全体の一部であるという深い感覚とともに起こる。ヨガとか禅とか、インド哲学とかを思えばよい。全体性wholenessにたいする憧れが生まれるという(p.82)。この辺りは達成型の個人主義に対するアンチテーゼの面が強く、特に欧米の文脈ではよくあるものなので、さほどまともに受けあう必要はないだろう。
進化型組織は、生命体に比喩で語られる。ちなみに達成型組織は機械、多元的組織は家族(p.90-93)。進化型組織へ移行するための突破口break-through(本書の用語だが、進化型組織の特徴くらいに思えばよい)が3つある。自主経営self management、全体性wholeness、進化目的evolutionary purpose。この三つをキーワードにして、そのために進化型組織がどのような仕組みを備えているのかは簡単にまとめられていて(p.385-389)、そのリストは極めて参考になる。
ちなみに進化目的は本書では存在目的と訳されている。これは著者の意を最大限汲むか、分かりやすさを取るかだが、単純に組織の存在目的(存在理由raison d'être )とは言いにくい。生命体としての組織がどこへと進化していくか、なぜ変化を行うかという意味合いがある。すなわち生命体の比喩を使いつつも、組織は人間が作るものだから目的を持つ。生物学的進化そのものには目的はない、という議論に馴染んでいる人には、進化目的という言葉はちょっとピンとこない。というより、生命体の比喩はそもそも失敗しているとも言える。
自主経営というのも苦しい訳語だが、現場の小さなチームが意思決定を行うこと。その意思決定の程度は並大抵のものではない。マネジメントの権限そのものが委譲される。よって進化型組織にはミドルマネジメントがない。法務や財務など、いわゆるバックオフィスのスタッフもない。通常の会社では各現場がそうしたバックオフィス機能を持つより、本社に集約したほうが規模の経済が働くのだが、そうした考えはない。またスタッフ機能によって現場をコントロールするという幻想を捨てなければならない(p.121)。法務知識などは現場が知識を身に着けるか、外注して助言を求める。スタッフ機能によるコントロールの代わりに、相互信頼による統制が効いている。他人を見習う習慣と仲間からの圧力が、階層性よりもはるかにうまくシステムを統制するのだという(p.133-136)。この、お互いを徹底的に信頼すること、というのが進化型組織の一番の特徴だろう。明確には書かれていないが、相互信頼こそが鍵。進化型組織は従業員を信頼する。マクレガーのY理論だ(p.182f)。
よって自主経営とは、ソビエト的な中央計画委員会から、組織内に自由市場経済を成功させる原則を持ち込むということだという(p.141f)。ただ、自由市場経済が相互信頼によって成り立つかどうかは議論の的だろう。比喩は成功しているだろうか。マネジメントなどの管理業務が一人のメンバーに集中すると、いつのまにか階層的組織のやり方に戻ってしまうリスクがある。ビュートゾルフでは管理業務をいつでも全員で負担しておくようにしている。FAVIではチームリーダーと呼ばれる一人の人に管理的な仕事が集中しているが、誰もがいつでも他のチームに移れるようになっている(p.152f)。意思決定はそれぞれが行うが、利害関係者のすべてに助言を求めることが要求されている。ただし、助言には従わなくても良く、コンセンサスではない(p.165-171)。最後にはその人・チームの意思決定をみなが信頼し、尊重する仕組み。
ソーシャルネットワークなどで他人と結びつくことに慣れている、ミレニアム世代の方が自主経営に馴染んでいるかもという指摘(p.232-234)は面白い視点。
全体性という特徴については、私利私欲を仕事に持ち込まないことが鍵となる。他人の妬みや羨み、足の引っ張り合いをなくす。自分の中の何かを我慢して仕事を行う必要はない。自分らしく仕事をできるように、オフィスを整えること。犬を連れてきたり、子供を連れてきてもよい。エゴを排除すると言っても、無私無欲が要求されるのではない。私たちは利己的でなく、完全に自分らしさを保ちながら、組織の進化目的の達成に向かって努力することができる。勤務中に自分を一部でも拒絶する必要はない(p.412)。こうしたことを実現するために、紛争解決プロセス、ミーティングルール、オフィスビルの工夫、人事制度などがある(p.242-244)。
全体性のくだりは、やや違和感を覚える。どうも論調は、仕事する私とそうでない私(onとoff)の分離を問題視して、私という全体を取り戻そうという話になっている(その先に世界全体との調和というより大きな全体性の話が来る)。ただ、ポイントはエゴを仕事に持ち込まないことだろう。相互信頼は、ペルソナ間では無理なのだろうか?発達段階の話からする進化型段階での自我の超越、全体性のテーマから、進化型組織において全体性が持ち込まれているように見える。ポイントが少しずれている感覚を個人的には持つ。
進化目的は、従来型組織では経営理念だったりビジョンにあたるようなもの。ただ、進化型組織の持っている進化目的は、その組織のためのものというより、より広い文脈にある。社会的課題の解決のようなものが据えられる。その目的が達成されるなら、自分の組織が達成する必要すらない。容易に他の組織と組んでいくし、利益を追うことも目的としない。利益は目的を実現するにしたがって得られていく副産物だ。進化目的とは、自分の組織が世界の中で何を実現したいのかという独自の目的を、従業員が感じ取り、自分の会社が生命体であると捉えるようなものだ(p.470f)。
こうした進化目的に向けて、進化型組織は目標数値などは設定しない。進化型組織の視点からは、未来は予測できないもの。目標数値の設定は意味がない。アジャイルなやり方が主(p.352-358)。こうして進化型組織は状況に合わせて変化し続ける。変革は自然に起こるため、チェンジマネジメントなどいう考えすらない(p.362)。ちなみに、こうした環境の変化への適応、数多く繰り返される実験的な事柄、変化の行方の分からない統制のなさといったところが、進化型組織の生命体との比喩の理由であり、「進化型」という名前の由来だろう(p.485)。だが、進化とは単独の生命体=組織で起こることではなく、世代を通じた淘汰において起こるもの。ちょっとずれがある。
最終章は進化型組織の作り方。進化型組織は一度できてしまえば、もう安泰なのではない。CEO(進化型組織は階層がなく最高責任者という概念はふさわしくないが、いわゆるCEO)や取締役会の理解がなければ、進化型組織もすぐに従来型に戻ってしまう(p.420-427)。三つの特徴のうち、一番達成しやすいのは進化目的。進化目的に関する慣行は、最も容易に受け入れられる可能性が高い(p.472)。もっとも難しいのは自主経営。自主経営を採用する進化型組織に移行する時に最も難しい問題は、ミドルマネジメント、シニアマネジメント、スタッフ部門の抵抗にどう対抗するかだ(p.455-457)。こうしたものができていない、スタートアップ企業は一番、進化型組織にしやすい。そもそも立ち上げの直後の段階はどこも自主経営される傾向がある。進化型組織はゼロから立ち上げる方が作りやすい(p.434)。
進化型組織への移行の仕方は三つ書かれる。創造的カオス、ボトムアップの再設計、既存テンプレート(p.457-461)。創造的カオスでは、ビッグバン的にトップダウンで組織を作り変えてしまう。このこと自体は進化型組織とは相いれないのだが、法措定暴力のようなものだ。ボトムアップの再設計では皆の同意を取りながら、組織を変革していく低速なアプローチ。既存テンプレートはすでにある進化型組織の形(ホラクラシーなど)を導入する。実際はこの導入の過程がトップダウンかボトムアップになり、前二つに吸収される区分だろう。
進化型組織が、自主経営・全体性・進化目的を実現するために持っている仕組み、慣行(p.438-443)。自主経営について3つ、助言プロセス、紛争解決メカニズム、同僚間の話し合いに基づく評価と給与決定プロセス。全体性について4つ、安全な空間を作るための基本ルール、オフィスや工場の設計、オンボーディング・プロセス(新人教育)、ミーティングで実践すべき慣行(参加者のエゴを防ぐ手段)。進化目的について2つ、採用プロセス、「誰も座らない椅子」(組織そのものの意見を代弁する)。よくまとめられている。
進化型組織への全面的な移行は、記されている通りリーダーやオーナーの世界観によってなされる。一見、従業員には関係のない話に見える。ただ、徐々にでも進化型組織の特徴を取り入れていなかければならないように、時代環境は要求しているのも確か。自分のチームで進化型組織の慣行をいくつか採用してみるなど、できることもあるだろう。誰もが一度は読んで、みずからの属する組織(それは企業に限らず、地域コミュニティーや学校かもしれない)について考えるべき。豊富な視点を提供する、貴重な一冊だろう。
- 2019年9月29日に日本でレビュー済みAmazonで購入人々の可能性をより一層引き出す組織とはどんな組織で、それを実現するにはどうすればよいか。これが本書のテーマで、新しい組織論のコンセプト「進化型(ティール)組織」を紹介した本だ。
進化型組織には、従来の組織とは異なる大きな特徴がある。階層やコンセンサスではなく同僚との関係性で組織が動く「自主経営(セルフ・マネジメント)」、ありのままの自分をさらけ出し同僚・組織・社会との一体感を持てるような風土や慣行がある「全体性(ホールネス)」、組織の存在性と向かう方向を常に追求する「存在目的」の3つである。
「自主経営」の部分を掘り下げてみよう。かなり衝撃的である。部下を支配する上司が存在しない。本部スタッフは驚くほどの必要最少人数。経営陣はなく、ミーティングもほとんどない。組織図や肩書もない。意思決定は管理職の指示やコンセンサスではなく、チーム内の「助言プロセス」「紛争解決プロセス」で決まる。解雇も報酬もチーム内で決まる。まさしく「自主経営」だ。これで果たして組織が回るのかと思わずにはいられない。
「全体性」はどうか。人間関係を円滑にするための、ベタな行事の開催や慣行。自分のありのままの姿をなるべく多く自覚し、会社で同僚たちの前に思い切ってさらけ出す。それにより、豊かで生き生きと意味のある生活を送れるようになるという。「存在目的」では、まさに存在目的そのものが目標であることから、競争などは存在せず利益という概念は「空気みたいなもの」とされ、目標も設定されないという。本書では、これらの特徴を実践する企業の実例が、従来の組織(その発展の順に衝動型・順応型・達成型・多元型として解説される)と比較されつつ詳細に紹介される。
ボリュームが相当ある本で、内容の繰り返しと共に飽きは来る。が、私の所属する組織と比較しつつ、各個人はどうやったら自分らしく振る舞えるだろうかなどと考えながら、ゆっくり読み進めた。日本では、上司や他人に判断を任せて自分で決めきれないビジネスマンが多いように感じられ、この点が日本で進化型組織が普及するネックであると感じた。
- 2019年8月14日に日本でレビュー済みAmazonで購入「ティール組織」は今まで読んだビジネス書の中でベスト5に入りそうです。
正直、話題になっていた当時はただの組織論の本かと思ってましたが、内容を読んで驚愕しました。
これは大げさに言えば人類の進化、人と集団の歴史、文化人類学を描いた本です。
関連書籍を上げるとすると「サピエンス全史」や「銃・病原菌・鉄」がよいのではないかと思いました。
この「ティール組織」はマッキンゼー出身のフレデリック・ラルー氏によって書かれた本です。
本の中ではこれまでの人類が歩んできた組織構造を「レッド」、「アンバー」、「オレンジ」、「グリーン」、「ティール」と色に分けて定義されています。
簡単に説明すると「レッド」の組織はギャングのような力による支配の組織、強いリーダーによる恐怖の組織です。次の「アンバー」は階級的なピラミッド、「オレンジ」は多国籍企業のような実力主義、「グリーン」は家族的で人間関係を重視する組織と続いていくのですが、最後の「ティール」がまさに本題の「ティール組織」となっており、本の定義によると、マネージャーやリーダーなどの役職が存在せず、上司や部下といった概念もなく、各自が自立して動き、平等に権限を持ち成立する組織となっています。
それぞれの段階が層になっており組織の変遷を表しています。
これがかなり自分の中では腑に落ちますし、非常にわかりやすく納得感もあります。
まあもちろん本の中でも同じ会社でも単純に色分けできないと書かれていますが、本の中では世界中のティール組織を実現している会社が紹介されており、同じティールを実現している会社でも多様性があり興味深かったです。
まだこれは実践していかないとわからない面も多々ありますが、これからの組織や会社を考える上で考えさせられました。
ぜひマネージメント層などだけではなく、末端の一般従業員から個人事業主まで、自分の人生をどう世の中の組織と歩んでいくか考えるキッカケになると思うので、すべての働く方に読んでほしいです。
- 2019年3月23日に日本でレビュー済みAmazonで購入大多数の企業人にとって自分の会社や日本社会がダメな理由を組織体制と社会変化の観点から整理できることが、いま本書がブームになっている理由と言えるだろう。ただし、巷がティールな組織ばかりになる時代は遠い未来の話だと著者も語っている訳で、「これからはティール組織の時代だ!」と簡単に盛り上がる風潮は、著者の言葉をちゃんと読んでない軽薄な反応だと思う。それくらい、本書で書かれていることは難易度が高い。
先日、あるワークショップで翻訳者の嘉村氏が、人のものを盗むような人間ばかりの社会ではティール組織は成立しないだろうとお話されていたのを拝聴した。ホテルや公的機関の中であっても、しょっちゅうモノが無くなる途上国で仕事をすることが多い僕はこの意見に大賛成なのだが、著者が強調するトップの意識改革と同じくらい、ティール組織は組織内の人間一人ひとり(=すなわち全員)が「大人であること」が求められるはずである。(著者が繰り返し、本書で性善説を唱えている点は象徴的だ。)実際、紹介されているティールな会社の事例では、早々に辞めていく人間もある一定割合でいるようだが、社会全体でそのような「大人」がマジョリティになる時代は本当に来るのだろうか?例えば、それは、経済成長の果実が世界中に生き渡った後、人類全体の富への欲望が一巡して意識変革が終わった状態の社会で可能になるかもしれないが、でも今の時代の貧富のバランスは逆に歪みが拡大しているのでは?
生物学のメタファーの下、少人数の自律的チームのクラスターが自己生成的に組織を作ることに成功すると、結果的に見事に環境に適応して時に驚異的な利益を生むというビジョンは、もちろん面白い。だが、生物のメタファーを徹底するなら、あらゆる環境で生存できる生物が存在しないように、たとえ少人数チーム(細胞)からなる自己生成的な自律組織であっても、環境に適応できず死んでしまうということは普通にあり得るはずだ。もしかしたら、ティール組織とは、「奇跡的に珍しい環境下」でしか生存していない、新種の希少種みたいなものである可能性はないだろうか?特に後半での著者の周到な書きぶりからは、そのようなドライな認識が僕には感じられるのだが。
という具合にウダウダ書いたが、それでも僕がこの本で一番面白かったのは、遠い未来にしかやってこないと著者も語るユートピア、「ティール社会」を描いた最終章である。(ニュー・アカブームの最後尾で思春期を送った中年オサーンの僕は、ドゥルーズ=ガタリのリゾーム論を思い出した。)未来の社会変革について書かれた本で、ワクワクできる本というのは、そうはない。










![[イラスト解説]ティール組織――新しい働き方のスタイル](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/81FUQaueApL._AC_UL116_SR116,116_.jpg)




![[新訳]HOLACRACY(ホラクラシー)――人と組織の創造性がめぐりだすチームデザイン](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71IMIIl-ROL._AC_UL165_SR165,165_.jpg)
![ソース原理[入門+探求ガイド]――「エネルギーの源流」から自然な協力関係をつむぎ出す](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/81v3qfMQqEL._AC_UL165_SR165,165_.jpg)