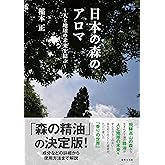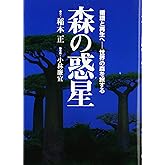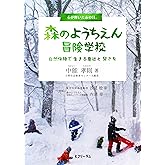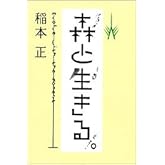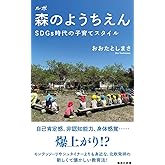狩猟採集(縄文)、農耕(弥生)、工業化(産業革命)時代、そして情報化・AI・コロナ時代への流れが、
ご本人の貴重な体験エピソードをベースに思想、哲学、科学の流れも交えて丁寧に整理整頓されています。
また流れをいかに主体的にパラダイムシフトさせてゆくべきか、私たち自身に考えさせてくれる一書です。
以下↓”はじめに”の一文です。
読みながらきっと、色々思い当たる節があると思う。それらを周りの人と共有したり試行したりされると、
さらなる新しい発想や、新しい道が開けるのではないかと期待して、本書を上梓させていただいた。
最終章第6章では「森と共生進化する方法」として8つの提案がまとめられ、
壮大な流れも”身近なライフスタイル”へとうまく合流、着地していくので安心です。
8つの提案の①~⑥はこれからの「地方創生」「SDGs」政策などで進めてほしいですが、
➆と⑧は、すでに私たちによって現在進行形 です。
➆意外と忘れがちだが、個人の家にある庭木も重要だ。
私はどの街を歩いても、それぞれの家の門や前庭や塀越しにある樹が気になる。
庭師に美しく刈り込まれているのも良いが、
何気なく柿の木が1本とか、しだれ桜が1本というのも良い。
それぞれの家がそれぞれの想いで木を育て、暮らしを豊かにしようとする心根が伝わってきて嬉しい。
⑧ベランダや玄関先に、植木鉢で小さな木や苗を植えているのも見かける。
木ではなくても草花や、時に野菜を植えている人もいる。
そのような小さな苗でも植物を身近に置き、大切にし、
それを子供や周囲の人にそれとなく伝える事が意外と大切な気がしている。
その気持ちを森全体へ繋げ、そして日本から世界の森へと思いを飛ばしてほしい。
かってメディア論のマクルーハンはメディアの発達によって、地球上の隅々まで情報が伝達され、
同じ情報を共有する、「グローバル・ヴィレッジ」(地球村)が生まれることを予測しましたが、
ローカルな地元の自然や伝統を大切に、世界の森と繋がることに目を開けば、
個性がつぶされることもなく、心は日々、健やかそう。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

脳と森から学ぶ日本の未来 単行本 – 2020/8/6
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
アインシュタイン、夏目漱石、SDGs、
ウイルス、縄文、AI、ブラックホール……
すべてつなげると、自然と調和した新しい生き方が見えてくる!
新型コロナウイルスをはじめ、自然災害、気候変動など、今世界ではさまざまな問題を抱えています。本書では、そんな私たちが今いる世界をどう捉え、どう考えたらいいのかを探ります。森と都会を行き来するトヨタ白川郷自然學校設立校長で東京農業大学の客員教授が、人類史、生命史から宇宙論までトータルな視点で世界を見つめます。
Q1、地球上で一番種類が多い生きものは?
Q2、アインシュタインの相対性理論が意味するものとは?
Q3、地図を逆さまにしてみると、日本はどう見える?
地図をひっくり返して見てみると日本列島は緑豊かな国で、地球史を振り返ると落ちこぼれの魚が人類への道を切り開いてきたがわかるのです。明るい日本を目指すために、今知っておきたいことを伝えます。
ウイルス、縄文、AI、ブラックホール……
すべてつなげると、自然と調和した新しい生き方が見えてくる!
新型コロナウイルスをはじめ、自然災害、気候変動など、今世界ではさまざまな問題を抱えています。本書では、そんな私たちが今いる世界をどう捉え、どう考えたらいいのかを探ります。森と都会を行き来するトヨタ白川郷自然學校設立校長で東京農業大学の客員教授が、人類史、生命史から宇宙論までトータルな視点で世界を見つめます。
Q1、地球上で一番種類が多い生きものは?
Q2、アインシュタインの相対性理論が意味するものとは?
Q3、地図を逆さまにしてみると、日本はどう見える?
地図をひっくり返して見てみると日本列島は緑豊かな国で、地球史を振り返ると落ちこぼれの魚が人類への道を切り開いてきたがわかるのです。明るい日本を目指すために、今知っておきたいことを伝えます。
- 本の長さ352ページ
- 言語日本語
- 出版社WAVE出版
- 発売日2020/8/6
- 寸法21 x 14.8 x 2.5 cm
- ISBN-104866212896
- ISBN-13978-4866212890
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
出版社より
目次一覧

脳と森から学ぶ日本の未来を探してみませんか?
本書は「共生進化」という考え方をベースに、日本と人類の幸福な未来に向けてパラダイムシフトするにはどうしたら良いかを理科系や文科系、心や自然などジャンルを超えて、さまざまな視点から探ります。
日本の未来に向け、「共生進化」を始めることでメディアや世の中の考え方が変わり始めたら、あなたがより自由になれる道が開けるでしょう。
大自然や建築物など、著者が訪れた国々の壮大な写真をカラーで掲載!

英国マルボロで出会えた椅子

ロシア正教の木造の教会

ボルネオ島の熱帯多雨林のラフレシア

46種の木をコンパクトに紹介!
「日本人として知っておきたい木46種」を著者がセレクト!
日本には深くて幅広い木の文化があります。紹介した各種の木の生態系での問題や、都市環境との問題、さらにそれぞれの樹種の使い方をよく吟味してください。思いもよらぬ樹の使い方がもっともっと発見されるかもしれません。

理解しやすい構成
参考写真やグラフなど、大きくて見やすい図解を使った丁寧な説明で、わかりやすく解説をしています!
商品の説明
著者について
稲本 正 Tadashi Inamoto
1945年富山県生まれ。69年立教大学理学部物理科卒業、その後物理科に勤務。74年岐阜県・高山市に移住、76年岐阜県・清見村にオークヴィレッジを移転。87年環境総合プロデュース会社オークハーツ設立。94年『森の形 森の仕事』で毎日出版文化賞受賞。『森の惑星プロジェクト』開始。トヨタ白川郷自然學校設立校長。東京農大客員教授。(一社)日本産天然精油連絡協議会専務理事。岐阜県教育委員。著書に、『緑の生活』(角川書店)、『森の博物館』(小学館)、『日本の森から生まれたアロマ』(世界文化社) 、『森の旅 森の人』(世界文化社) その他 多数。
1945年富山県生まれ。69年立教大学理学部物理科卒業、その後物理科に勤務。74年岐阜県・高山市に移住、76年岐阜県・清見村にオークヴィレッジを移転。87年環境総合プロデュース会社オークハーツ設立。94年『森の形 森の仕事』で毎日出版文化賞受賞。『森の惑星プロジェクト』開始。トヨタ白川郷自然學校設立校長。東京農大客員教授。(一社)日本産天然精油連絡協議会専務理事。岐阜県教育委員。著書に、『緑の生活』(角川書店)、『森の博物館』(小学館)、『日本の森から生まれたアロマ』(世界文化社) 、『森の旅 森の人』(世界文化社) その他 多数。
登録情報
- 出版社 : WAVE出版 (2020/8/6)
- 発売日 : 2020/8/6
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 352ページ
- ISBN-10 : 4866212896
- ISBN-13 : 978-4866212890
- 寸法 : 21 x 14.8 x 2.5 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 160,928位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 49位社会学の論文・講演集
- - 1,754位日本史一般の本
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.2つ
5つのうち4.2つ
115グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
イメージ付きのレビュー
星5つ中5つ
これからの難しい時代に生きるために、森が人間の脳にどのようにアクセスして正常化できるかということを示唆してくれる一冊です。
この本は今まで読んだどの本よりも「森と人類」の関わりについて学問的に偏ることなく丁寧に書かれていて、だからこそ時間をかけて読みたいと思える本です。 誰もが断片的に理解して、それでも纏めていくことが難しいテーマについて、整理整頓され、物事の本質を理解して書いてくださっています。 人々が利益のため、経済のために自分の脳を働かせるのをやめてただ盲従してしまったことが大自然とのバランスを失わせ、様々な軋轢を生んでいます。五感から切り離された脳は孤独です。 その孤独で暴走してしまう脳で行われている事がまた世界を混乱に陥れているとしたら、短時間で五感を散り戻すことのできる「森」は全生物に与えられた「恩寵」であり、そこと繋がることは世界と繋がる事だとこの本は示唆している様に感じています。 何度でも読みたい本です。
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2021年8月16日に日本でレビュー済みAmazonで購入立教大学物理学の教員を辞めて、岐阜県飛騨の山奥に住み、オークヴィレッジという木工会社を1975年に作った。「100年かかって育った木は100年使えるものに」という循環型の持続可能な方向を提案し、同時に生活全般で木を有効利用すべく「お椀から建物まで」というスローガンを掲げる。
広葉樹の植林活動を行い、地域の森林資源活用と日本産アロマに関する研究開発をしている。2005年にトヨタ白川郷自然學校の初代校長となる。文字通り、森とともに生きている人である。
本書を読んだ。うーん。読むのにひどく時間がかかった。「脳」と「森」というかけ離れたテーマを論じていて、文系と理系の枠を超えて、論じている。またわかりやすく説明しようとして、饒舌な感じもする。世界の森を駆け巡り、そして様々な人に会う。その人脈の広がりに目をみはる。
本書は生命と生物史、縄文、人類史、脳の機能、宇宙論、ブラックホール、SDGs、則天去私、梵我一如、共同幻想、そして共生進化と、小さな生命の始まりから宇宙にまで広げる。「宇宙は私であり、私は宇宙である」と言う。ある意味では、稲本正の世界観の集大成ともいえる書である。
今までに考えたことのないような視点もありいい気づきを与えられた。
地球上に存在する生物は、約175万種が確認されている。そのうち動物は約130万種。動物の約70%が昆虫を含む節足動物であり約95万種いる。地球上の半分以上が虫なのだ。維管束植物は約29万種。人類を含む脊索動物は、約7万種。生物の多様性といっても、意外と少ない。
生物の全体の重量は、約550ギガドン。そのうち植物は約450ギガドンで約80%で、細菌は約70ギガドンである。動物は、全重量の0.5%でしかない。この品種数と重量のデータはおもしろい。
裸子植物は約800種しかないのに、被子植物は約28万種ある。つまり花を咲かせ実を結ぶのにパートナーがいるのだ。昆虫や鳥に蜜を与える代わりに、花粉を運んでもらっている。
現在問題となっているのは、ミツバチが消えつつあるのだ。農薬の中でも「ネオニコチノイド」がハチを殺している。もしハチがいなくなると食料生産の3分の1が消えるという話もある。とりわけ、ニホンミツバチの減少が激しいという。ニホンミツバチは森の樹々や草花から蜜を集め、その蜜は「百花蜜」と言われ、味が濃厚であるという。確かにレイチェル・カーソンの世界が生まれている。
日本の森林面積のうち、スギ、ヒノキなどの針葉樹林は約41%。山を木材製造工場にしてしまった。そのため花粉症が日本国民病となる。
植えて、30〜70年になるので、建材として使える時期に来ているが、放棄されているところが多い。
日本の原生林は3%以下であり、広葉樹の2次林は約55%。これも放置されたままだ。これをどう手入れしていくかが、現在の大きな課題となる。日本の木材自給率は、1955年には約95%だったが、1970年になると約40%台に落ち込んだ。現在は、木材の自給率が約30%になっている。ふーむ。あまり木材の自給率など考えたことがなかった。森の再生が大きなテーマだろう。
隈研吾が、木材に注目して、木を使った公共施設を作るという試みは、森を再生させる上でも重要だ。稲本正は、「森と共生進化すること」を提案している。
木の文化は、縄文人が積極的に取り入れていた。青森県の三内丸山遺跡(約5900-4200年前)では、縄文人が直径90cm、長さ30mくらいのクリの木を使って、6本柱建造物を作っていた。そのような建造物は、石川県の真脇遺跡、富山県の不動堂遺跡にもある。縄文時代は、主食としてクリを使っていたようだ。佐藤洋一郎は、そのクリは遺伝的バラツキが少なく、縄文人が植林した園芸種であると指摘している。日本の農業はクリの育てることから始まった。三内丸山遺跡からは、緑豆、ヒョウタン、シソ、エゴマなどが見つかっている。縄文時代は、狩猟採集と菜園式農業を組み合わせた文明を創出していた。約3000年前の縄文時代後期にはすでに大陸から稲作がきていたことも確認された。福岡県の板付遺跡、佐賀県唐津市の菜畑遺跡などから、炭化米や土器に付着したモミの圧痕、水田跡、石包丁、石斧といった農具、用水路、田下駄等が発見されている。
日本の歴史から見ると、有機栽培をして、菜食主義的な生活が江戸時代まで行われていたことになる。肉を食べるようになったのは、明治からだ。
筆者のなぜ植物の葉は、緑であるかという考察も面白い。葉が緑に見えるのは、緑を反射しているからに過ぎない。だったら、緑を反射するとは、光合成をする上で不利になる。なぜ全部の光線を吸収しなかったかと疑問を持つのがいい。そうすれば、葉は真っ黒になるはずだった。
木から積極的にアロマを取る話も貴重だ。木はなぜアロマを発生するのか。それは自分自身を守るためである。森の活用の一つだ。46種の木の紹介がいい。放置されている森をどう再生するかは、これからの大きな課題となるだろう。
本書は、いろんな示唆があって、読むのは難儀であったが、おもしろかった。
これからは、森を守る体験と昆虫が好きになる体験こそが、SDGsとなっていくだろう。
- 2021年1月16日に日本でレビュー済みAmazonで購入自然科学から哲学、そして量子力学に至る広いテーマについて書かれていて、
読み進めていくうちに読者は壮大なスケールの世界に置かれている事に気が付く。
目次を見ると、学んだこともないような内容ばかりだったので、ついていけるか不安だったが、著者の「わかりやすさ」に徹した文章に救われた。
誰にでもわかるように、扱う項目によっては、前提となる知識から説明するところなど、「木」というものに対峙してきた人間の温和な優しさが感じられる。
一番興味深かったところは、量子力学的な視点で見る自然について書かれた辺り。
現代の最先端ともいえる量子力学は、物事の不確実性を証明したわけで、
これは、"根拠をしめせばその先にある未来が確実"となる(因果的決定論)を否定する理論であり、まさにパラダイムシフトのキーはこの点にあると思いました。
しかし、確実なものによって安心したい私たちにとって、それを受け入れるにはまだ相当時間がかかるはずです。環境破壊のスピードから考えて、人間にあまり猶予は持たされていない現実のなかで、私たちはどのように思想をシフトしていくべきか、そのヒントがちりばめられた傑作だと思います。
- 2022年11月21日に日本でレビュー済みAmazonで購入楽しみにしてたので、わざわざ新品を買ったのに、帯がぐしゃぐしゃで残念な気持ちになりました。
内容は、まだ途中ですが、ちょっと難しい。。。という印象ですが、とても興味深いです。
- 2020年10月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入カズオ・イシグロの『日の名残り』からの引用で、グッと引き込まれてしまった。
「全能の神がさ、人間を……その……植物みたいに作ったら、どうだったろう。そのほうがよかったかもしれない。ね? 大地にしっかり根を張ってさ。そうしたら、戦争だの国境だのなんていう問題は、最初からありえなかったんだ」
…(略)…
「しかし、そのような場合でも、君のような人間は必要だよね。伝言を取り次いだり、お茶を運んだりさ。(略)」
本書は、脳と森から、未来を創ることを構想している。脳と森??
扱っている分野は、物理学、生物学、文化人類学、哲学、文学と多岐にわたるのだけど、様々な知の巨人の言葉や作品の引用が面白くて、どんどん読み進んでしまう。著者の稲本さんは、知識や経験の広さや深さはもちろんすごいのだけれど、存在(Being)が素敵だ。
内容について、とりわけ興味を惹かれたのは、縄文時代の多様性を紐解く第3章。稲本さんは、この時代に「木の文明」があったとする。世界中で王権が成立し、戦争に明け暮れる中、日本では自然と一体になり豊かな文化を持つ社会があった。丸太船を作り、数百人が共同作業で木造建築を作り、漆を高い技術で使いこなし、栗などを植栽をして食を得る。
僕自身、いろんな土地を回って、“4000年前の漆“など縄文時代の話を聞くことがあるのだけど、それらのピースが物語の中に収まった気がする。
この第1の木の文明の後、4世紀ごろから、国中で狂ったように古墳を、実に20万基も造った土木の文明になる。いつまで続くのかと思ったら、607年に聖徳太子が法隆寺を造った時に、国中がハッと目が覚め、第2の木の文明が始まった。そして今は?また土木の文明にいる。
この章の最後にある「日本人として知っておきたい木 46種 生活文化を支える木」が楽しい。例えば、漆のところを読むと、“ジャパニーズ“という言葉に“漆器を使う人“という意味があると書かれている。
第3の木の文明は始まるのか。それはどんな形で。
稲本さんが思い描くのは、自然と人間の「共生進化」だ。
本書には共生進化についていろんなヒントがある。吉本隆明の共同幻想論が、最新の情報科学や脳科学と出会っていたらどうなるだろうか、という問いなどは刺激的だ。そして、兆しはいろいろ見えていると思う。自分がやっていること、関心があることについて、新たな広がりや関連性が見出せることもあると思う。自然のゆったりした時間の中で、また読んでみたい。
- 2021年3月7日に日本でレビュー済みAmazonで購入非常に良い本だった。
これからの人間社会と自然のつながりの在り方について,素晴らしい洞察が示されていた。
小学生の息子たちは,都会のコンクリートの監獄でなく,著者が紹介している里山のような,緑に囲まれた環境の中で育てたいものだ。
市場主義的な大量消費社会の限界には,誰もが気付いている。
われわれはもう,それには耐えられない。
きれいな空気を吸いに出かけよう。